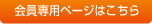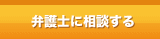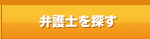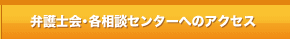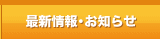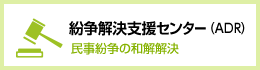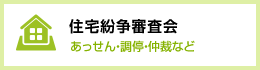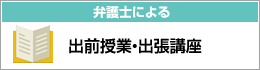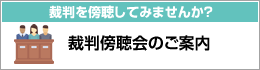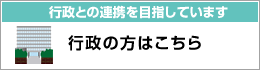~戦後80年の憲法記念日5月3日を迎えて~
日本国憲法は、国家の暴走による人権蹂躙、そしてアジア・太平洋諸国に2000万人以上(日本人約310万人)もの犠牲者をもたらした第二次世界大戦の惨禍という『現実』への深い反省を踏まえ、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」て制定されました。
日本国憲法は、この決意を実現するため、基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を三大原則と定めました。すなわち、日本国憲法は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」(11条)と確認し、表現の自由・生存権等の基本的人権を保障しています。また、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(前文)と確認し、国会議員は全国民から選挙されたもので構成され、国会・内閣・裁判所もその権威は国民に由来するものとしています。さらに、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」(9条)との戦争放棄を基礎とする平和主義を確認しています。これらは将来にわたる理念でもあります。
現在、戦争を直接に体験したことのない世代が多くなっています。しかし、語り継がれてきた『現実』はもとより、絶えることなき世界各地の戦争・紛争からは、その惨禍は、いまなお私たちに生じている『現実』です。むろん、第二次世界大戦同様の状態が私たちの日常生活に直接生じているものではありません。しかし、近時のウクライナ・ガザ地区をはじめ世界各地の戦争・紛争で自らの或いは親しい家族や友人らの命が凄惨かつ一瞬にして奪われる『現実』に接すれば、第二次世界大戦により当時の人々が心の底から感じたであろう戦争の惨禍という『現実』への深い反省と再び戦争を起こさないとの決意は、現在の私たちも同様に感じることができ、かつ、そのように確信されるものです。日本国憲法の原則や理念が危機的状況にあるといわれます。政府による集団的自衛権行使の容認や敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有といった憲法9条に反する立法や施策が進められていること、現代においても日々の衣食住の確保や文化的な生活すら困難となる現状などが生じていることなどの『現実』からは、改めて日本国憲法の原則と理念が確認されるべきです。
日本国憲法は、前文と103条の条文となっています。国家の運営を担う人々(内閣総理大臣をはじめとする大臣や国会議員、裁判官等)に私たちの基本的人権を擁護する義務を課し、権力の濫用を防止することによって私たちの権利・自由を守っています(立憲主義)。戦後80年の憲法記念日5月3日を迎えるにあたって、是非、例えば、憲法の条文を声に出して読んでみる、自ら書き或いは打ち込んでみるなど、1つ1つの条文に触れていただきたいと思っております。第二次世界大戦の惨禍という『現実』への深い反省を踏まえ「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」て制定された先人たちの思いが感得されるはずです。日本国憲法の原則と理念は、守り引き継がれるだけでなく、その時々の国民から理解・共感され積極的に選択され続けていくべきものです。
私たちも、憲法記念日にあたって改めて日本国憲法の原則と理念、ひいては日本国憲法の制定経過を深く認識し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、日本国憲法の原則と理念を実現するよう尽力していきます。
2025年(令和7年)5月3日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平