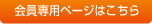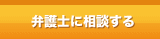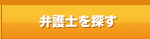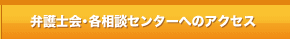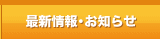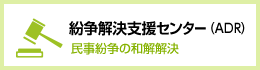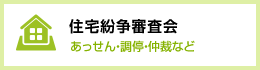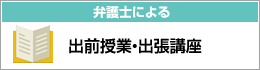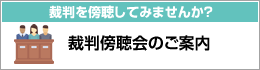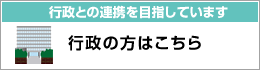昨年、いわゆる袴田事件について再審無罪判決がなされ、確定した。また、いわゆる福井女子中学生殺人事件についても、再審開始決定がなされ、確定した。
両事件の審理を通じて、現行刑事訴訟法における再審に関する定め(以下、「再審法」という。)の不備が明らかになった。多くの事件について再審手続が長期化し、えん罪被害者の救済が遅々として進まない原因は、各事件固有の事情にあるものではなく、現在の再審法が抱える構造的問題にあるというべきである。
現在、再審法改正の必要性は、広く社会に認識されるに至り、昨年3月11日に超党派で結成された「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」の参加国会議員数は、昨年10月に行われた衆議院選挙前の時点で全国会議員の過半数を超え、衆議院選挙を経た本年1月7日時点で363名にのぼる。また、全国の500を超える地方議会や地方自治体の首長、各種団体からも、再審法改正への賛同が相次いで寄せられている。
このような情勢において、本年2月7日、鈴木馨祐法務大臣は、再審法の見直しについて近日中に法制審議会に諮問することを明らかにした。
しかし上記の通り、再審法が抱える構造的問題の存在は、国会議員の間でも整理・共有されつつあるところ、これから法制審議会に諮問されたとすれば、審議を経て結論を得るまでには、さらに年単位での時間を要する可能性が高い。長期の審議によって、再審法が抱える深刻な問題が矮小化ひいては否定されかねない。
また、法務省は、現在においても再審法改正に積極的であるとは到底言えない。
すなわち、昨年10月8日に出された袴田事件に関する検事総長談話や、昨年12月26日に最高検察庁が公表した袴田事件に関する検証結果報告書に照らすと、法務・検察当局は現行再審法の改正の必要性があると考えていないことが明白である。法制審議会の事務局は法務省が担うものであり、法務省刑事局は主に検察官によって構成されている。委員の人選も恣意的になされかねない。再審法改正の議論を、法務省の諮問機関である法制審議会に委ねるべきではない。
現在の再審法は、誤判からの救済手段としての意義・役割をほとんど果たせておらず、長年にわたり再審は「開かずの門」あるいは「駱駝が針の穴を通るより難しい」と言われてきた。その結果、えん罪被害者の多くは高齢化し、えん罪被害者の膨大な日々時間が奪われ続けている。なかには、無念のうちに獄死したえん罪被害者も存する。えん罪は国家による最大の人権侵害の一つであり、再審法の不備が人権・人道の問題であることは言うまでもなく、一刻も早い救済が求められる。
法の不備によってもたらされる人権・人道の問題について、立法府はこれを是正する責務を負う。苦しむえん罪被害者が多くいる現在の状況を踏まえるならば、議員立法によって、一刻も早く再審法改正を実現するべきである。
そして、袴田事件をはじめとするこれまでの再審事件の経過を踏まえれば、再審法の構造的な問題点は明確である。すなわち、なされるべき法改正の要諦は、当会が2023(令和5)年7月27日開催の臨時総会決議及び2024(令和6)年9月26日会長声明において指摘したところの下記3点である。
1 再審請求手続における証拠開示の制度化
2 再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止
3 適正手続を保障する再審請求手続規定の整備
よって、当会は、えん罪被害者の迅速な救済を実現するべく、改めて、これらの内容を含む再審法の改正を、議員立法によって速やかに実現することを求める。
2025年(令和7年)2月19日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 藤 田 祐 子
提 案 理 由
第1 はじめに
2024(令和6)年9月26日、静岡地方裁判所は、いわゆる袴田事件について、袴田巖氏に対し再審無罪判決を言い渡し、確定した。また、2024(令和6)年10月23日には、名古屋高等裁判所金沢支部にていわゆる福井県女子中学生殺人事件について、再審開始を認める決定がなされ、確定した。
これらの再審事件を通じて、再審制度の構造上の不備が改めて明らかになった。
えん罪は国家による最大の人権侵害の一つであり、法の不備は直ちに解消されなければならない。現在の情勢を踏まえるならば、議員立法によって、一刻も早く再審法改正を実現するべきである。
第2 袴田事件の経過
袴田事件で被告人とされた袴田巖氏は、1980(昭和55)年11月19日に最高裁で上告が棄却された。以後40年以上にわたり死刑囚として死の恐怖にさらされながら、以下の通り長きにわたる裁判を強いられた。
1981(昭和56)年4月20日に申し立てた袴田氏の第1次再審請求は、2008(平成20)年3月24日、最高裁で特別抗告が棄却されて終了した。
その後に申し立てられた第2次再審請求において、2010(平成22)年9月に至り、ようやくいわゆる「5点の衣類」のカラー写真等が検察官から初めて任意に開示された。弁護団が、その精査を行った上、新たな証拠開示請求及び主張をした結果、2014(平成26)年3月27日、静岡地方裁判所は、再審を開始し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田氏は釈放された。
しかし、検察官が再審開始決定に対し即時抗告し、2018(平成30)年6月11日、東京高等裁判所は、再審開始決定のみを取消し、弁護側が特別抗告した。
2020(令和2)年12月22日、最高裁判所は、高裁決定を取消して差戻し、2023(令和5)年3月13日、東京高等裁判所は、2014(平成26)年の静岡地方裁判所の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。かかる決定に対し、検察官が特別抗告をしなかったため、再審開始決定が確定した。
裁判のやり直しを行う再審公判は、静岡地方裁判所にて、2023(令和5)年10月27日から計15回開催され、2024(令和6)年5月22日、検察は死刑を求刑、弁護団は無罪を主張して結審した。
2024(令和6)年9月26日、静岡地裁は袴田氏に再審無罪判決を言い渡し、同年10月9日に検察官が上訴権を放棄したことにより、同判決が確定した。
第3 福井県女子中学生殺人事件の経過
1986(昭和61)年に発生した福井女子中学生殺人事件では、2004(平成16)年7月に第1次再審請求がなされ、2011(平成23)年に名古屋高等裁判所金沢支部が再審開始決定を出したにもかかわらず、検察官が異議を申し立て、2013(平成25)年3月に再審開始決定が取り消された。
2022(令和4)年10月に第2次再審請求がなされ、裁判所の訴訟指揮により、警察保管の捜査報告メモを含む計287点の証拠が新たに開示され、名古屋高等裁判所金沢支部は、2024(令和6)年10月23日、新旧証拠を総合評価した上で、再び再審開始決定が出され、確定するに至った。
第4 再審制度の構造的問題
1 両事件の審理経過が示すもの
袴田事件及び福井県女子中学生殺人事件(以下、「両事件」という。)における審理経過は、裁判所の積極的な訴訟指揮に基づき検察官から証拠開示がなされない限り、再審制度が機能しないことを示している。また、再審開始決定に対する検察官による不服申立により、再審審理が著しく長期化したことも顕著である。
当会が、2023(令和5)年7月27日開催の臨時総会決議及び2024(令和6)年9月26日会長声明において指摘した再審法の構造的な問題点が、両事件の審理経過から露わになった。すなわち、現在の再審法における構造的な問題点の主たるものは、以下の三点である。
2 証拠開示制度の不備
第一に、証拠開示制度の不備が挙げられる。現行刑事訴訟法では、再審における証拠開示制度が整備されておらず、裁判所の裁量に委ねられているため、再審開始を導く重要な証拠が再審請求人に開示される保障がない。両事件が象徴するように、再審開始決定を得た事件においては、長期にわたって不提出証拠の開示が行われず、再審請求手続の中で初めて開示された検察官の手持ち証拠の中に、再審開始を導く重要な証拠が含まれていた、というものが少なくない。このような事態は、そもそも有罪判決を言い渡した裁判が、公平且つ公正な裁判であったのかに強い疑問を抱かせるものである。再審請求手続においては、十分な証拠開示制度を整備することが急務である。
3 検察官の不服申立の許容
第二に、検察官による不服申立が許容されていることが挙げられる。近年、再審開始決定に対する検察官による即時抗告や特別抗告が行われることが多く、両事件がまさにそうであったように、再審開始が遅延し、えん罪被害者の速やかな救済が阻害される事態が続いている。職権主義的審理構造のもとで、利益再審のみを認め、再審制度の目的をえん罪被害者の救済に純化した現行の再審請求手続においては、検察官は「公益の代表者」として裁判所の審理に協力する立場に過ぎないのであるから、検察官に不服申立権を認める必要はない。仮に、検察官が有罪主張を維持するのであれば、再審開始決定後に開かれる再審公判で立証を尽くせば足りるはずである。
検察官の不服申立権は廃止されるべきである。
4 審理手続きに関する規定の不存在
第三に、現行刑事訴訟法に再審請求審の手続規定、とりわけ手続の進行に関する明文の規定がないことが挙げられる。それゆえ、現行法のもとでは、審理の進行が各裁判所の裁量に委ねられ、積極的な訴訟指揮を行う裁判官に配点されるまで、再審請求審が機能不全に陥る事態が顕著である。両事件ともに、積極的な訴訟指揮を行う裁判官が担当したことにより審理の方向性が如実に変化した。審理手続きに関する規定が整備されていないことにより、ときに「再審格差」と呼ばれる裁判官の訴訟指揮における格差が生じている。
したがって、手続き規定の整備は不可欠である。
第5 現在の状況
1 再審法改正に向けた機運の高まり
昨年確定した袴田事件無罪判決等から再審法の問題点が広く社会に認識されるようになり、再審法改正に向けた機運がこれまでにない高まりを見せている。
昨年3月11日に超党派で結成された「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」の参加国会議員数は、昨年10月に行われた衆議院選挙前の時点で全国会議員の過半数を超え、衆議院選挙を経て今なお増加している。現在、宮城県選出国会議員の大半がかかる議員連盟に参加している。
また、全国の地方議会や地方自治体の首長、各種団体からも、再審法改正への賛同が相次いで寄せられており、宮城県議会においても昨年10月17日に「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」が全会一致で採択された。
主要な全国紙(読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞)や、NHKを含めた全国の報道機関が社説や映像で再審法の早期改正の必要性を訴えている。
2 法務省・検察当局の対応
このような情勢の中、本年2月7日、鈴木馨祐法務大臣は、再審法の改正を近日中に法制審議会に諮問することを明らかにした。
しかし、昨年10月8日に出された袴田事件に関する検事総長談話や、昨年12月26日に最高検察庁が公表した袴田事件に関する検証結果報告書に照らすと、法務・検察当局は現行法における問題の所在を十分に理解していないものと評価せざるを得ない。
すなわち、昨年10月8日に出された袴田事件に関する検事総長談話では、判決まで長期間を要したことを謝罪しつつも、再審開始決定に対して即時抗告したことには触れなかった。重要証拠を長時間公開していなかったことにも言及しない一方で、裁判所の判決理由に対し「大きな疑念」を、捜査機関による証拠のねつ造が認定されたことに対しては「強い不満」をそれぞれ表明した。
また、昨年12月26日に最高検察庁が公表した袴田事件に関する検証結果報告書は「内部検証」の限界を露呈した。すなわち、再審手続が極めて長期化したこと、第1次再審請求から証拠開示に至るまで約30年を経過したこと、検察官が即時抗告に及んだことについて、いずれも検察官には問題が無かったと評価し、再審法改正の必要性についても言及されなかった。袴田事件が無実である袴田氏を死刑囚として50年近くにわたって拘束し、日々死刑執行の恐怖にさらし続けた重大な人権侵害をもたらした「死刑えん罪事件」であることを法務・検察当局が真摯に受け止めているものとは到底言えない。
このように、法務・検察当局が再審法改正に消極的であることが顕著な状況において、法務省の諮問機関であるところの法制審議会に再審法の改正を諮問した場合、審議の内容が現行法の問題点の検証及びその改正の必要性に明確に絞られず、争点が曖昧なまま回数を重ね、審議を経て結論を得るまでには、さらに年単位での時間を要する可能性が高い。また、適切な再審法の改正が必要という結論が導き出されない可能性も高い。こうしたことから、長期の審議によって、再審法が抱える深刻な問題が矮小化されたあげく、抜本的な再審法の改正がなされない結果に終わりかねない。
このような懸念が広く共有されていることから、法制委審議会への諮問は、法務省・検察当局が、再審法改正の機運の沈静化を企図したものではないかと指摘する報道もなされている。
3 速やかな救済の必要性
えん罪は国家による最大の人権侵害の一つである。再審法の不備が人権・人道の問題であり、一刻も早い救済の必要性があることは言うまでもない。
現在、両事件のほかにも、大崎事件や日野町事件など直ちに再審を開始すべき事案が存在するものの、構造的な不備に起因する「再審格差」によって、再審の扉は開かれていない。現在の再審制度は、誤判からの救済手段としての意義・役割をほとんど果たせていないと言わざるを得ず、一刻も早く是正されなければならない。
両事件をはじめとする過去のえん罪事件から、現在の再審法の問題の所在は明確である。①再審請求手続における証拠開示の制度化、②再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止、③適正手続を保障する再審請求手続規定の整備が急務である。
国会内の情勢としても、多くの国会議員の賛同が得られている状況であり、超党派で結成された「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」の参加国会議員数は、本年1月7日時点で過半数を超える363名にのぼる。その後も、参加国会議員数は増加しており、議員立法で再審法の改正を実現できる環境は整っている。
法の不備による人権・人道の問題について、立法府はこれを是正する責務を負う。現在の状況を踏まえるならば、法制審の審議に委ねることなく、議員立法によって、一刻も早く再審法改正を実現するべきである。
第6 結語
よって、当会は、えん罪被害者の迅速な救済を実現するべく、改めて、これらの内容を含む再審法の改正を、議員立法によって速やかに実現されることを求める。