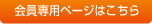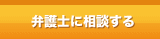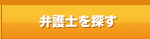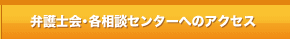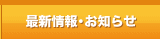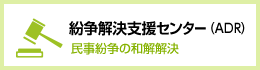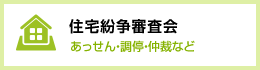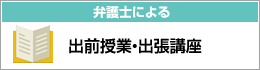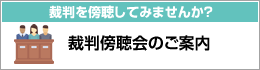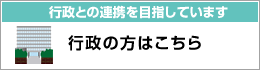子どもがひとりの人間として尊重される社会の実現のためにあらゆる手段を講じることを求める決議
1 2024年は、子どもの権利に関する初めての国際文書である「ジュネーブ子どもの権利宣言」採択から100年、国連総会での「子どもの権利条約」採択から35年、そして日本での同条約批准から30年が経過した節目の年であった。
「子どもの権利条約」は、子どもが固有の権利を有する主体であることを明確にし、それまで保護の客体とされていた子ども観を大きく転換すると同時に、成長の過程にあるがゆえに保護や配慮が必要な子どもならではの権利を保障するべく、子どもの最善の利益や、生命、生存及び発達に対する権利の保障、子どもの意見の尊重(意見表明権)などを定めている。「子どもの権利条約」の内容を実現するために、日本では、2023年にようやく子どもの権利保障のための基本的かつ総合的な法律である「こども基本法」が施行され、同法に基づき政府全体の施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が策定された。
しかし、現在の日本においては、子どもの権利が十分に保障されているとは言い難い。
2 まず、家庭においても学校においても、全ての子ども達の権利が保障されている状況にあるとは到底言えない。近年、児童虐待件数は増加の一途をたどっており、ヤングケアラーについても問題が表面化するなど、子どもが家庭において十分にその権利を守られず、苛酷な状況におかれている現状が報告されている。
学校現場においては、いじめが重大事態に至っているとされるケースが増加しているほか、子どもに不合理な制約を課す校則の存在や、教師等による児童生徒への体罰、不適切指導が行われる例も後を絶たない。また、学校に登校しない、又はすることができない不登校児童生徒数は近年激増しており、学校における学習や成長発達の機会を享受できていない子どもたちが多数存在している現状がある。
また、社会全体における貧困、障がい者や少数者への偏見や差別、性差別やジェンダーバイアス等に根ざす機会の不平等などの問題が深刻化する中で、成長発達過程にあり、自らを守るべく意見を表明したり自己の権利を行使したりすることが難しい子どもたちは、大人たちよりも苛酷な状況に置かれることを余儀なくされる傾向にある。
このような中で、生存の権利すら行使できずに自ら生命を絶たざるを得ない状況におかれている子どもたちがおり、子どもの自死者数は過去最多の水準が続いている。国連子どもの権利委員会は、日本政府に対し、子どもが社会の競争的性質によって健全な発達を害されずに子ども時代を過ごせることを確保するよう、繰り返し勧告している。こうしたことからも、現在の日本においては、子どもの生命・生存・発達の権利、教育を受ける権利や平等が十分に保障されているとは言えない。
3 こうした現状を改善し、子どもの権利保障を実現するためには、子どもに関わる大人たちが子どもの最善の利益を優先的に考える必要がある。そのためには、大人たちが、子どもの最善の利益の重要性を理解し、それを実現する発想を持つことが不可欠であり、特に子どもに関わる職業に就く者に対してはそのような啓発や研修を行っていくことが必要である。
また、「こども基本法」第1条は「社会全体としてこども施策に取り組む」と明記しており、子どもの権利保障の観点から社会全体の問題の改善にも取り組んでいく必要がある。すなわち、苛酷な状況におかれている子どもの周囲の大人への経済的、社会的援助や、子どもに関わる立場にある大人たちへの支援や環境の改善が不可欠である。
4 そして、子どもが権利主体であることからすれば、子どもの発達に応じた子ども自身の意見表明権を保障し、尊重することが極めて重要であるが、そのためには、単に子どもに意見を述べる機会を与えればいいというものではなく、子どもが声を上げやすい環境を作ることや、子どもの発達段階等に応じた適切な説明や相談に応じることも必要である。また、そもそも子どもが意見を形成すること自体に対する支援と同時に、子どもに意見を述べることを強要しないこと、また、子どもの意見を否定したりないがしろにしたりしないことも重要である。
しかし、日本では、このような子どもの意見表明権の理解や法的保障が不十分で、意見聴取制度の対象も社会的養護下の児童に限定されており、家庭裁判所における子どもの手続代理人制度も十分に活用されていない。また、政府は、「子どもの権利条約」の発効によっても教育関係法令等の改正は必要ないとした平成6年5月20日付文部事務次官通知を維持するとしており、学校における子どもの意見表明権も保障されているとは言えない。
こうした状況の中で、子どもの意見表明を実現し、権利侵害から子どもを救済するためには、「人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した政府から独立した子どものための人権機関(オンブズパーソン等、独立した調査権限、環境調整や勧告、提言等を行う権限を持つ、中立・公正な第三者機関としての相談、救済機関。以下、「相談救済機関」という。)の創設が重要である。
地方自治体レベルにおけるオンブズパーソン等の子どもの「相談救済機関」の設置は、「こども大綱」においても国が取り組みを後押しする重要事項の一つとされているが、宮城県及び県内市町村にはそのような機関はいまだに設置されていない。この点、当会は、2018年6月、仙台市に対し、「子どもの人権を守るための第三者機関の設置等を求める提言」を行った。これを受けて仙台市いじめ等相談支援室S-KET(エスケット)が設置され、相談や救済の窓口として一定の効果をあげており、その設置の意義は大きいが、いじめ等対応という限定的な位置づけや、独立性の担保、調査・勧告権限等に条例の根拠がないこと等の点において上記相談救済機関と同等であるとは言えない。
「子どもの権利条約」の内容を実現するためには、地方自治体においても、子どもの権利に関する総合的な条例の制定を行うことが重要である。条例には、上記相談救済機関の設置に係る事項のほか、⑴子どもが権利主体であることを明記すること、⑵子どもの権利は、子どもが成長発達するために必要不可欠なものであり、義務や責任の対価として与えられるものではなく、子どもの権利に対して義務や責任を負うのは大人であることに留意すること、⑶子どもの意見表明権の保障や施策決定に際し子どもが参加できる仕組みを作ること、などが盛り込まれるべきである。
5 よって、当会は、
(1)国に対し、改めて、子どもの権利条約に基づく子どもの権利保障を推進し、子どもがひとりの人間として尊重される社会の実現を目指して、子どもの意見表明権を家庭・学校を含むあらゆる場面で保障すること、教育関連法令やその運用等について子どもの権利保障の関係から見直し検討を行うこと、子どもに関わる職業に就く者に対して子どもの権利に関する具体的な研修を実施すること、子どもの相談救済機関の設置、その他、子どもの権利を保障するためのあらゆる手段を講じることを求める。
(2)宮城県及び県内の各市町村に対し、子どもの権利条約の内容を実現するため、子どもの権利に関する総合的な条例の制定を行い子どもの相談救済機関を設置すること、当該条例制定に際して、⑴子どもが権利主体であることを条例に明記し、⑵子どもの権利は、子どもが成長発達するために必要不可欠なものであり、義務や責任の対価として与えられるものではなく、子どもの権利に対して義務や責任を負うのは大人であることに留意すること、⑶子どもの意見表明権保障及び施策決定に際しての子どもが参加できる仕組み構築などの内容を盛り込むことを求める。
当会もまた、今後も子どもの権利を保障するための施策についての提言、啓発、その他子どもに寄り添う諸活動を通じて、子どもがひとりの人間として尊重される社会の実現に向けて尽力していく所存である。
2025年(令和7年)2月19日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 藤 田 祐 子
提 案 理 由
第1 はじめに
子どもは、固有の権利を有する権利の主体であり、保護されたり管理されたりする客体としてのみ扱われる存在ではなく、ひとりの人間として尊重されなければならない。
昨年(2024年)は、「ジュネーブ子どもの権利宣言」採択から100年、国連総会での「子どもの権利条約」採択から35年、そして日本での同条約批准から30年が経過した節目の年であった。
「子どもの権利条約」は、上記のように子どもが固有の権利を有する主体であることを明確にし、それまで保護の客体とされていた子ども観を大きく転換するとともに、保護や配慮が必要な子どもならではの権利を保障するべく、子どもの権利を考える上で重要な4つの原則として「差別の禁止」、「子どもの最善の利益」の原則、「生命、生存及び発達に対する権利」の保障、そして「子どもの意見の尊重(意見表明権)」を定めている。
これらの内容を実現するために、日本では、2023年に、子どもの権利保障のための基本的かつ総合的な法律である「こども基本法」が施行され、「こども家庭庁」が設置された。そして、同年12月22日、「こども基本法」に基づき、政府全体の子ども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定された。
しかし、現在の日本においては、以下において詳述するとおり、子どもの権利が十分に保障されているとは言い難い。
第2 子どもに対する権利の制約や侵害等を含む苛酷な状況
1 家庭等における状況
保護者から児童(18歳未満の子ども)に対して、身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること、わいせつな行為をする、又はわいせつな行為をさせること、保護者としての監護を著しく怠ること、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと等は、児童虐待と定義されているところ(児童虐待の防止等に関する法律第2条)、児童相談所での児童虐待相談対応件数は毎年増加しており、こども家庭庁の統計調査によると、2022年中に、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は214,843件で過去最多となっており、2021年度の児童虐待による死亡事例は68例(74人)と、一時期よりは減少したものの、子どもの命が保護者によって奪われる事態が未だに多数発生している。
また近年は、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者(子ども・若者育成支援推進法第2条7号)である「ヤングケアラー」の問題も表面化するなどの現状も報告されている。
2 学校等における状況
文科省の調査結果(令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)によると、学校現場においては、いじめの重大事態(いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める事態若しくはいじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める事態=いじめ防止対策推進法第28条参照)の発生件数は1,306件(前年度919件)であり、前年度から387件(42.1%)増加し、過去最多となった。
さらに、子どもに不合理な制約を課す校則の存在や、教師等による児童生徒への体罰、不適切指導も後を絶たない。
上記文部科学省の調査によれば、小・中学校における不登校児童生徒数は346,482人(前年度299,048人)であり、前年度からは47,434人(15.9%)増加しており、11年連続の増加であり過去最多となった。不登校児童生徒数の増加については、様々な要因や背景が考えられるものの、学校における学習や成長発達の機会を享受できていない子どもたちが多数いることは事実である。
このように、学校でも権利の制約を受けたり権利を侵害されたりしている子どもたちが多数存在している。
3 子どもたちを取り巻く貧困、差別、偏見等による不平等の問題
また、社会全体において貧困、障がい者や少数者への偏見や差別、性差別やジェンダーバイアス等に根ざす機会の不平等などの問題が深刻化している。そのような社会の中で、立場の弱い子どもたちは大人たちよりもそうした問題による不利益を被りやすく、苛酷な状況に置かれやすい。社会におけるあらゆる歪み、問題の影響を最も強く受けるのは、まだ成長発達過程にあり、自らを守り権利を行使することが難しい子どもたちである。2022年時点で相対的に貧困の状態にある子どもの割合は11.5%、特にひとり親世帯の貧困率は44.5%にも及ぶところ(令和6年版子ども白書)、貧困の状態の中におかれた子どもたちは、自らの意思や能力とは無関係に、健康、生活の質、学習、その他あらゆる機会を奪われており、子どもの権利の視点から見ると生存や発達の権利が制約を受けている。
教育の機会や進路選択の自由に関しても、外国籍や外国にルーツを持つ子どもの小学校不就学率は5.7パーセントという高い数値になっている(令和6年8月8日文科省発表)。また、女性生徒の大学進学率は令和6年時で54.5パーセントであり、男性生徒の60.7パーセントに比して低い数値であるだけでなく、男性生徒と比較して女性は大学に進むとしても地元で進めばよいとされがちであり、男性に比べて地元を離れにくいなどといった、女性生徒の大学進学率の数値には表れない、現実の進路選択の制約もある。また、障がいや貧困を原因として自由な進路を選択することができず、進学等を断念せざるを得ない事例もある。
このように、国籍や出自の違いその他の少数者に対する差別や偏見、性差別やジェンダーバイアスなどにより、教育をうける機会の不平等などのしわ寄せを子どもたちが受けている。
4 子どもの自死者数の高止まり
このような中で、自ら生命を絶たざるを得ない、生存の権利すら行使できない状況におかれている子どもたちが多数存在するという極めて深刻な事態が生じ、小中高生の自死者数は高止まりしている。
厚生労働省によれば、小中高生の自死者数は2011年以降、毎年300人を超えるようになり、2020年に大きく増加して400人を大きく超え、その後、2022年には統計開始以来最多の514人となり、2024年(暫定値)にはさらに過去最多となる527人にまで達した。国連子どもの権利委員会は、日本政府に対し、過度に競争的な学校システムの見直し等を繰り返し勧告しており、第4回・第5回政府報告書審査に基づく総括所見においては、教育の問題に止まらず、生命、生存及び発達に対する権利に関して、子どもの生活全般について、社会の競争的性質により子ども時代や発達を害されることなく過ごせることを確保するように求めている。
こうしたことからも、現在の日本においては子どもの生命・生存・発達の権利、教育を受ける権利や平等が十分に保障されているとは言えない。
第3 子どもの最善の利益を考えるために必要な施策
1 子どもに関わる大人たちへの支援
こうした現状を改善し、子どもの権利保障を実現するためには、子どもに関わる大人たちが、子どもの最善の利益の重要性を理解し、それを実現する発想を持つことが肝要であり、子どもに関わる職業に就く者に対する啓発や研修等が必要不可欠である。
また、「こども基本法」第1条が、「全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組む」と明記しているのであるから、個別の問題において子どもの最善の利益を考えるだけでなく、上記のとおり社会全体の問題が子どもにしわ寄せとして現れることを踏まえ、苛酷な状況におかれている子どもの周囲の大人への経済的、社会的援助や子どもに関わる立場にある大人たちへの支援や環境の改善も不可欠である。
教育環境については、不合理な校則の強要も含め過度に管理的な体制など学校におけるストレスフルな状況を軽減し、学校が子どもにとって権利が保障され、伸び伸びと学び成長できる場である必要がある。そのためには、子どもたちと日々接し、全人格的なかかわりの中で教育にあたる教員らの環境も保障されている必要があり、教員らの苛酷な労働環境、待遇の改善が必要である。また、上記改善は、学校においていじめその他の問題が発生した際に、迅速かつ適正な対応がとれるような体制を構築するためにも不可欠である。同時に、学校に通えない状態にある子どもたちや、国籍や障がいなどの要因により社会的に少数あるいは弱い立場に置かれている子どもたちに対する、学習の機会や進路選択の機会も保障されなければならない。
2 意見表明権の保障
また、子どもが権利主体であることからすれば、子どもの発達に応じた子ども自身の意見表明権を保障し、それを尊重することが極めて重要である。そのためには、単に子どもに意見を述べる機会を与えればいいものではなく、子どもが声を上げやすい環境を作ること、子どもの発達段階等に応じた適切な説明や相談に応じること、子どもが意見を形成すること自体に対して支援すること、子どもに意見を述べることを強要しないこと、また、子どもの意見を否定したりないがしろにしたりしないこと等が必要である。
しかし、日本では、このような子どもの意見表明権の理解や保障が不十分である。児童福祉法改正により社会的養護のもとにある子どもに対する意見聴取措置が制度化されたが、広く学校や家庭における子どもの意見表明権を保障する法制度は整備されていない。また、家事事件手続法により、家庭裁判所における紛争に際し子どもの意見を尊重するための子どもの手続代理人制度も創設されたものの、費用負担の問題もあり、その利用は家事事件数が増加し続けているにもかかわらず、著しく低調である。
また、学校においても、子どもの意見表明権は保障されているとは言えない。政府は、「子どもの権利条約」の発効によっても教育関係法令等の改正は必要なく、学校での子どもの意見表明権は理念を一般的に定めたものであり、校則は学校の責任と判断において決定されるべきものであるとした平成6年5月20日付文部事務次官通知を維持するとしている。しかし、子どもの権利条約やそれを受けて意見表明権を定めたこども基本法第3条3号、4号、同第11条及び第15条に照らしても、上記通知は撤回し、子どもの意見表明権を前提に教育関係法令を改めるべきである。
第4 子どものための相談救済機関(第三者機関)創設の重要性
こうした状況の中で、子どもの意見表明権を実現し、権利侵害から子どもを救済するためには、「人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した 政府から独立した子どものための人権機関(いわゆるオンブズパーソン等、独立した調査権限、環境調整や勧告、提言等を行う権限を持つ、中立・公正な第三者機関としての相談、救済機関。以下、「相談救済機関」という。)の創設が重要である。当会はこれまで、2024年2月22日付「国際水準に沿った人権保障を求める決議」、2020年2月22日付「個人通報制度の早期導入と国内人権機関の早期設置を求める決議」及び2011年7月22日付「各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に合致した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議」においても、繰り返し国内相談救済機関の設置を求めてきたが、上記のように子どもの権利の保障の必要性が一層高まっている現状を踏まえ、改めて、子どもの権利を守るための相談救済機関の設置を国に対して求めるものである。
地方自治体レベルにおけるオンブズパーソン等の子どもの相談救済機関の設置は、「こども大綱」においても国が取り組みを後押しする重要事項の一つとされているが、宮城県及び県内市町村においてはそのような子どもの相談救済機関はいまだに設置されていない。この点、当会は、2018年6月、仙台市に対し、「子どもの人権を守るための第三者機関の設置等の提言」を執行し、「子どもの人権を実質的に保障し,子どもの人権に対する侵害から子どもを守るための新たな制度として,独立した調査を行う権限を持ち,必要に応じて環境調整や関係機関に対する勧告・提言等を行うことができる,中立・公正な第三者機関を設置し,子どもの立場に立って運用してゆくこと」を求めた。これを受けて、仙台市においては、「仙台市いじめ等相談支援室。通称:S-KET(エスケット)」が設置された。S-KETには、仙台市内に居住する若しくは仙台市立の学校に在籍する子どもや保護者から多数の相談が寄せられており、臨床心理士や弁護士による相談、若しくは関係機関との調整が奏功するなどして問題が改善する例も多く、その設置の意義は大きい。しかしながら、「いじめ等」の対応という限定的な位置づけや、独立性の担保、調査・勧告権限等に条例の根拠がないこと等の点において上記相談救済機関と同等であるとは言えない。当会としては、仙台市を含む宮城県内の市町村並びに宮城県に対して、条例に根拠を持つ子どもの相談救済機関の設置を改めて本決議によって求める意義は大きいと考える。
そして、上記のような相談救済機関の設置を含め、「子どもの権利条約」の内容を実現するためには、地方自治体においても、子どもの権利に関する総合的な条例の制定を行うことが重要である。当該条例には、上記子どもの人権機関の設置に係る事項のほか、⑴子どもが権利主体であることを明記すること、⑵子どもの権利は、子どもが成長発達するために必要不可欠なものであり、義務や責任の対価として与えられるものではなく、子どもの権利に対して義務や責任を負うのは大人であることに留意すること、⑶子どもの意見表明権の保障や施策決定に際し子どもが参加できる仕組みを作ること、などが盛り込まれるべきである。
第5 結語
我々弁護士は、個々の相談、依頼を受けたり、少年事件の弁護人や付添人として少年に関わったりする中で、あるいは児童相談所の顧問やスクールロイヤー等の立場で事案に関わる中で、権利を侵害され、苛酷な状況に置かれている子どもたちに繰り返し出会う。
特に、非行や問題行動を行った子どもたちは、虐待、貧困、差別、家庭や学校での居場所のなさなど、幾重にも困難を背負い、まさに社会の歪みを一身に受けて、およそ子どもの権利が守られてこなかった者が多い。
非行や問題行動を行った子どもたちに関する報道やSNSの投稿においては、子どもたちの問題性のみが取り上げられたり、子どもたちのみが非難されたりすることが少なくないが、これらの問題が、子どもたちの権利を守ることができなかった大人や社会の問題であるという事実は、決して看過されてはならない。
当会は、上記のように権利の制約や侵害をされ、苛酷な状況に置かれる子どもたちを救済し、また、今後、そのような状況に置かれる子どもたちを一人でも減らすべく、子どもたちがひとりの人間として尊重され、その権利が保障される社会を実現することが急務と考える。そのため、国に対して、上記の諸点を含む子どもの権利を保障するためのあらゆる手段を講じることを求めるとともに、当会もまた尽力していく決意を明らかにする本決議を提案する次第である。