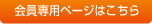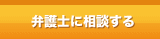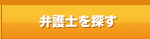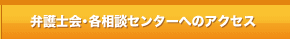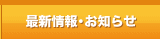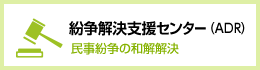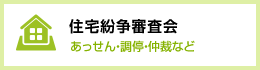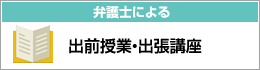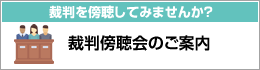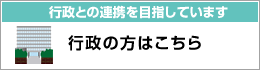石破内閣は、本年3月7日、日本学術会議(以下「学術会議」という。)会員候補者6名の任命拒否問題(2020年10月)を放置したまま、「国の特別の機関」とされている学術会議を廃止し、国から独立した法人格を有する組織としての特殊法人「日本学術会議」(以下「新法人」という。)を新設する日本学術会議法案(以下「本法案」という。)を国会に提出した。本法案は、5月13日に衆議院で可決され、これから参議院での審議が始まる。
しかし、本法案は、当会が本年2月7日付け会長声明において指摘してきた問題点や学術会議が示した懸念点を払拭していない。そのため、時の政治権力から独立して科学的根拠に基づく政策提言を政府に対して行うナショナル・アカデミーである学術会議の根幹をなし、学問の自由(憲法23条)に基づく独立性・自律性が損なわれるおそれが大きい。
戦前、政府は、滝川事件(1933年)や天皇機関説事件(1935年)等を通じて学問に対する弾圧・統制を行った。そして、国家による学問統制の下で、科学者は兵器の研究・開発等により戦争に協力していった。この戦前から戦時下における反省を踏まえ、日本国憲法は表現の自由(21条)や思想・信条の自由(19条)とは別に学問の自由を定めることにより、科学者のコミュニティ(学問共同体)の自治を制度的に保障した。学術会議は、このような憲法の趣旨に基づき、政府から独立した自律的組織としてのナショナル・アカデミーとして創設されたものである。
ところが、本法案は、科学者の総意の下で示された現行法前文の使命を踏襲せず、学術会議が職務を「独立して」行うという現行法3条の文言を削除し、政府を含む外部が会員選任や組織運営に対し介入する新たな仕組みを幾重にも盛り込んでいる。
第一に、会員選任についての外部からの介入である。すなわち、現行法(7条2項、17条)では学術会議の自主性・独立性が認められているのに対し、本法案は会員候補者の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会を設置しているため(本法案26条、31条)、会員候補者の選定が外部の者の意向に影響を受けるおそれがある。また、会員候補者の選定に際しては、会員のみならず、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることが義務付けられ(本法案30条2項)、諸外国の多くのナショナル・アカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション(現会員が会員候補者を推薦する方式)による選考方式が損なわれるおそれがある。
さらに、本法案は、新法人発足時の会員選考について、会長が任命する候補者選考委員会の委員には会員以外の者を想定し(本法案附則6条4項)、その任命に際して内閣総理大臣が指名する有識者と協議しなければならないとしているほか(同条5項)、同委員会が実施する会員予定候補者の推薦についても、会員のみならず、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から求めることを義務付けている(同附則7条3項)。新法人発足から3年後の会員選考においても、上記候補者選考委員であった者から会員候補者選定委員が選任されるため(本法案25条3項、本法案附則23条)、コ・オプテーションの実質が損なわれるおそれがある。
このような方法で選任された会員によって構成される新法人が、時の政治権力から独立した立場で科学的根拠に基づく政策提言を政府に行うという、これまで学術会議が果たしてきた任務を遂行することができるのかについては、大きな懸念を抱かざるを得ない。
第二に、活動面における政府からの独立の弱体化である。すなわち、本法案は新法人の政府に対する勧告権を維持しているものの(本法案39条)、現行法5条と比べて勧告事項が大幅に簡略化している。また、勧告権を支える組織運営の独立性については、①会員以外の者から会長が委員を任命し、中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成、組織の管理・運営などについて意見を述べる運営助言委員会(本法案27条、36条)、②内閣府に設置され、会員以外の者から内閣総理大臣が委員を任命し、中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(本法案42条3項、51条)及び③会員以外の者から内閣総理大臣が任命し、業務を監査して監査報告を作成し、業務・財産の状況の調査等を行う監事(本法案19条、23条)の設置、並びに内閣総理大臣の是正措置権限(本法案50条)により、大きく損なわれることになる。
第三に、財政基盤について、現行法は国庫負担の原則を定めている(1条3項)。しかし、本法案は、補助金の支出を政府の裁量に委ねている(本法案48条)。そのため、新法人は安定した財政基盤を欠くおそれがある。
本法案には以上のような問題点があり、十分に時間をかけて慎重に審議しなければならないにもかかわらず、衆議院内閣委員会はわずか3日間の審議で採決してしまった。同委員会では、政府に対し会議の独立性や自主性、自律性を尊重することや活動を萎縮させることがないよう必要な財政措置を行うことなどを求める附帯決議がなされたものの、本法案の問題を解消するものではない。
当会は、戦前及び戦時下の反省を踏まえて「平和的復興」(現行法前文)等を使命とし、学問の自由に基づく独立性・自律性を持って設立された学術会議が、戦後80年を迎えるときに廃止されることに強い危惧を抱かざるを得ない。
よって、当会は、学術会議の独立性・自律性を損なうおそれが大きい本法案に反対し、参議院において本法案の問題点を徹底的に追究し、問題点の改善がなされない限り廃案にすることを求める。また、今般、学術会議が推薦した会員候補者の内閣総理大臣による任命に関する法解釈の変更に関する行政文書の全面開示を命じる判決(東京地方裁判所2025年5月16日判決)がなされたことをも踏まえ、政府に対し、改めて2020年10月の学術会議会員候補者6名の任命拒否について説明責任を果たすとともに任命拒否に係る問題を是正してその正常化を図り、学術会議の独立性・自律性を尊重して相互の信頼関係を構築することを求める。
2025年(令和7年)5月22日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平