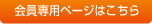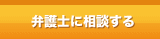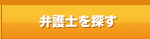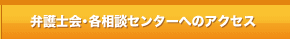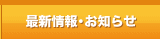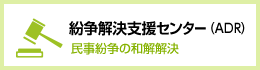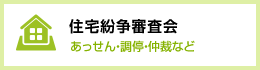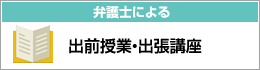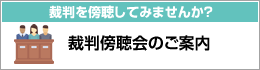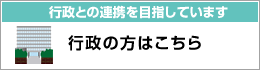佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定における不正行為に関する会長声明
本年(2025年)9月8日、佐賀県警察本部(以下「佐賀県警」という。)は、佐賀県警の科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)に所属する技術職員が、7年余りにわたりDNA型鑑定で虚偽の書類を作成するなどの不正行為(以下「本件不正行為」という。)を行っていたと発表した。
佐賀県警によると、この技術職員は2017年6月から2024年10月までに632件のDNA型鑑定を担当し、そのうち130件の不正行為が確認され、実際は鑑定をしていないのに実施したかのように装ったほか、鑑定後に試料のガーゼを紛失してしまい、それを取り繕うために新品でごまかしたこともあったとのことである。本件不正行為は、虚偽公文書作成罪、同行使罪及び証拠偽造等罪に該当する可能性の高いものである。
DNA型鑑定は、DNAの多型部位を検査することで個人を識別するために行う科学的手法であり、刑事司法手続においては被疑者・被告人と犯人の同一性を立証するために用いられる証拠になり得るものである。また、自白偏重によるえん罪事件の発生を防止するために捜査や公判においては科学的証拠が重視されているが、その中でもDNA型鑑定の結果は、より客観的な証拠として刑事裁判の立証において重要視されている証拠でもある。
しかし、DNA型鑑定の過程において不正があったということになれば、捜査や公判などの刑事司法手続の公正を著しく歪め、かえってえん罪事件を発生させてしまうことにもなる。
佐賀県警は、本件不正行為に関しその全てにつき捜査や公判への影響はなかったとしているが、捜査や公判への影響の有無や程度を問わず絶対に許されない。仮に、本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果が公判に証拠として提出されていなかったとしても、それは結果論に過ぎないし、逮捕勾留のために必要な疎明資料、被疑者に対する取調べのための資料及び検察官の終局処分のための資料など捜査の各場面において影響を与えた可能性は否定できない。
したがって、本件不正行為は、科学的証拠を重視する刑事司法手続に対する信頼を根幹から揺るがすものであって、当会はこれを強く非難する。
本件不正行為の検証について、佐賀県警は「第三者的な立場から監督する機関の県公安委員会があり、それに重ねる形で新たに設置する必要はない」などとして、第三者機関の設置の必要性を繰り返し否定している。
しかし、佐賀県公安委員会は、「DNA型鑑定における不適切事案の再発防止に向けた提言」を公表したものの、職員の倫理観のかん養、業務管理の徹底及び佐賀県警が警察庁からの重点的な業務指導を受けることを求めるにとどまり、本件不正行為の検証は何ら行われていない。警察庁も佐賀県警に対する特別監察を開始したものの、内部的な調査にとどまり、調査の公正や中立性、透明性が担保されるとはいえず、本件不正行為の実態を解明することは期待できない。
また、本件不正行為を行った技術職員の動機、DNA型鑑定における監督体制の不備などからすれば、DNA型鑑定の過程における不正は、佐賀県警のみの問題とは言えず、警視庁及び道府県警察本部に設置された科捜研においても同様の不正が生じうる状況にあることは強く疑われる。
さらに、DNA型鑑定における不正を防止するとともに、再鑑定による事後的な検証を可能にするためには、犯罪捜査の記録の管理及び保管を義務付けること並びに弁護人による事後的な検証を行うことができる全面的証拠開示制度を創設することが不可欠である。
よって、当会は、
① 佐賀県公安委員会に対し、直ちに捜査機関から独立した第三者機関を設置し、本件不正行為の詳細な事実関係、背景、捜査公判の帰趨に本当に影響がなかったか、また7年余りもの間、本件不正行為が看過されてきたことなどについて徹底した検証を行い、今後の再発防止策を策定すること
② 法務省、最高検察庁、警察庁及び警察庁を管理する国家公安委員会に対し、独立した第三者機関を設置し、警視庁及び道府県警察本部に設置された科捜研においてDNA型鑑定の過程の中で不正が存在しないかの調査すること及び調査結果の公表を求めるとともに、実施した調査結果を踏まえた十分な監督体制の構築を含む再発防止策を策定すること
③ 国に対し、事後的な検証を可能にするための鑑定資料を含む犯罪捜査の記録の管理及び保管を義務付けること及び全面的証拠開示制度を創設すること
を求める。
2025年(令和7年)10月23日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 千 葉 晃 平