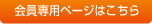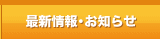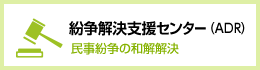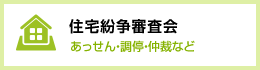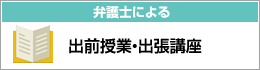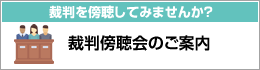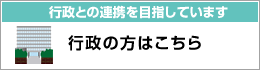2018年(平成30年)12月14日
仙 台 弁 護 士 会
会 長 及 川 雄 介
少年法の適用年齢引下げに反対する意見書
第1 意見の趣旨
少年法の適用年齢を現行の20歳未満から引き下げるべきではない。
現在議論されている刑事政策的措置により適用年齢の引下げによる問題を回避することはできない。
第2 意見の理由
1 はじめに
当会は、2015年4月24日、「少年法の『成人』年齢引下げに反対する会長声明」を公表し、少年法の「成人」年齢を引き下げることに反対する旨を表明した。
しかし、2017年2月には、民法の成年年齢引下げが議論される中で、法務大臣が法制審議会に対し、「非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方」とともに「少年法における『少年』の年齢を18歳未満とすること」を諮問するに至った。これを受け、現在、法制審議会の少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(以下「部会」という。)では、少年法の適用年齢を18歳未満とすることの是非、及び少年法適用年齢を引き下げた場合に採りうる刑事政策的対応を含めた犯罪者処遇策が議論されている。
そして、この間、2018年6月には、飲酒・喫煙、公営ギャンブル等に関する各法律については20歳を基準として現行の適用年齢を維持する一方で、民法の成年年齢を18歳に引き下げる内容の民法の一部改正法が成立した(2022年4月施行予定)。
このような状況を踏まえ、改めて、少年法の適用年齢引下げに関して意見を述べる。
2 少年法の適用年齢を引き下げるべきでないこと
以下では、現行少年法に対する評価を確認した上で、少年法の適用年齢を引き下げる理由がないこと、むしろ適用年齢引下げによる問題が大きく、引き下げるべきではないことについて述べる。
(1) 少年法の適用年齢を引き下げる理由(立法事実)がないこと
ア 少年法は有効に機能していること
現行の少年法は有効に機能しており、その評価については部会においても異論がない。
少年法は、少年の健全育成のため、その性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うことを目的としている。すなわち、成長過程、人格の形成途上にある少年の非行には、その資質と生育環境が大きく影響していることから、資質面の問題については性格の矯正を、生育環境に対してはその環境調整を、保護処分として行うことで、少年の健全育成を図ろうとするものである。このような保護処分が強制力をもって行われる根拠は、それが未成熟なために判断能力に乏しく非行に至った少年自身の利益にもなり(保護原理)、また、非行により他者の利益を侵害した若年犯罪者に対しては、刑罰を科すよりも改善教育を行うことで再犯防止対策となる(侵害原理)との考え方に基づく。
かかる立法趣旨に基づき、家庭裁判所等の関係機関は、人間行動科学に基づく審理と保護処分優先の処遇を実践してきた。全件送致主義・家庭裁判所先議の制度設計と、少年鑑別所による資質鑑別や家庭裁判所調査官による社会調査を中核とした審判手続の中で、少年の非行の原因を解明し、少年の健全育成の観点から本人にとって最も適切な処遇を選択する仕組みが、少年法制を有効に機能させている。
その結果、刑事裁判及び刑務所での処遇より、少年法に基づく処遇の方が、若年者の再犯防止にとっても有効であるということは、法務省等の実証的研究や調査・分析等によって裏付けられている。2014年中に出所した受刑者が2年以内に再犯に至り再入所した割合は18.5パーセントである一方、同年中に少年院を出た少年が2年以内に再入院した割合は11.4パーセントにとどまっている。同様に、2011年中に出所した受刑者が5年以内に再犯に至り再入所した割合は38.8パーセントである一方、同年中に少年院を出た少年が5年以内に再入院した割合は21.7パーセントにとどまっている。
このように、現行少年法の全件送致主義、調査官調査を中核とした審判手続及び少年院教育等の一連の枠組みが極めて有効に機能していることは、統計上も明らかであり、部会においても異論がなく、議論の前提とされている。
イ 少年事件が「増加・凶悪化」しているなどといった事実はないこと
少年法の適用年齢を引き下げるべき立法事実と一般に言われている事実は存在しない。
内閣府が実施した世論調査の結果を見ると、少年事件について、「件数が増加している」とか「凶悪化している」といった誤った印象が持たれているようである。
しかし、少年犯罪の件数が増加しているとか凶悪化しているといった統計データは存在しない。実際には、少年の検挙者数は毎年減少しており、少年による殺人・強盗・放火等の重大犯罪についても大きく減少している。また、検挙者数だけでなく、少年人口当たりの発生数も大幅に減少している。
このことは、前述のとおり、現行少年法のもとでの少年審判、保護処分といった少年法制が有効に機能していることを裏付けるものであるとも言える。
むしろ、非行を犯した少年の多くは、成長過程において多くのハンディを抱えていることが明らかとなっており、かかる少年には刑罰を科すことではなく、保護処分に付して個別的な指導・教育を行い、成長を支援することこそが、再犯防止のために必要なことである。
(2) 少年法の適用年齢を引き下げる理論上の必要性もないこと
ア 民法の成年年齢の変更は少年法の適用年齢を引き下げる理由とならないこと
今回の少年法の適用年齢引下げの議論は、公職選挙法の選挙権年齢の引下げ及び民法の成年年齢の引下げの議論と併せて議論されてきた。そして、少年法の適用年齢を引き下げるべきとする立場は、公職選挙法の選挙権年齢や、特に民法の成年年齢が18歳と引き下げられたことを前提に、一般的な法律において「大人」として取り扱われることになる年齢は一致させる方が国民にとって分かりやすい(「国法上の統一」)、などとして少年法の適用年齢も18歳に引き下げるべきだとする。
しかし、法律の適用年齢を考えるに当たっては、それぞれの法律の立法趣旨に照らして、法律ごとに個別具体的に慎重に検討すべきである。民法の未成年者制度が、取引行為を行う判断能力の不十分な未成年者を保護、救済することを目的にしているものであるのに対し、少年法は、前述のとおり、成長過程にある少年の非行に対し、保護処分として、性格の矯正や生育環境の調整を行うことで、少年の健全育成を図り、もって再犯を防止しようとするものであり、両者の趣旨目的は全く異なる。したがって、民法の成年年齢と少年法の成人年齢が異なることに何ら問題はなく、むしろ差異があって当然である。
また、実際に、未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法などの一定の法律については、民法の成年年齢引下げにもかかわらず、適用年齢の引下げが見送られている。このことからしても、「国法上の統一」が少年法の適用年齢引下げの理由とならないことは明らかである。
イ 立法経緯をみても民法と少年法の年齢の規定を整合させる必要はないこと
民法上の成年年齢と、少年法の適用年齢を一致させる必要がないことは、旧少年法改正の際の少年年齢「引上げ」の際の審議経過や年齢引上げの趣旨等からも明らかである。そもそも、旧少年法は少年を18歳未満としており、民法の成年年齢(20歳)とは元々一致していなかった。そして、旧少年法の少年年齢を20歳未満と引き上げる際、その趣旨については、18歳から20歳までの年齢層に一番犯罪が多く、かつこのような若い人の犯罪を減らすには刑罰のみでは不十分であり、保護の力が必要であるとの説明がされており(1948年第2回国会)、他方で、同国会の全審議過程を見ても、民法の成年年齢との整合性が理由にされたり、これとの関係が問題にされたりした形跡は一切ないのである。
また、上記少年法適用年齢引上げの理由とされたところは、現在においても妥当する。すなわち、現在でも検察庁が通常受理する少年被疑者のうち半数近くを18歳、19歳の年長少年が占めており、少年被疑者の中では、18歳、19歳の年長少年による犯罪が多い状況には変わりがない。したがって、これらの年齢層に対し単なる刑罰だけでなく保護により更生を促す必要性は現在も変わりはなく、今、民法等に合せて少年年齢を引き下げるとすれば、かつて少年法が改正され少年年齢が引き上げられた趣旨を没却し、過去の立法経過と矛盾、相反することになる。しかも、前述のとおり少年犯罪自体が減少傾向にある中で、その半数近くを占めている年長少年を少年司法手続から外すとすれば、現在有効に機能している少年法の保護主義による更生の機会の大半は奪われることとなる。
ウ 民法上の成年に対し少年法を適用することに、憲法上ないし法理論上の問題はないこと
(ア) 少年法適用年齢の引下げに賛成する立場からは、保護処分は少年の権利を制約する不利益処分でもあるところ、このような保護処分は、少年が類型的に未成熟で判断能力不十分であることから、国家が後見的に介入するという保護主義(パターナリズム)により正当化されている側面があるとして、親権に服さない民法上の成年者を類型的に保護主義(パターナリズム)に基づく保護処分の対象とすることは過剰な介入であるとする。
しかし、保護主義による国家の介入が許容される年齢は、民法の成年年齢を基準として一律に決まるものではなく、国家の後見的介入を必要とする程度や、内容、性質によって異なるものである。
民法上の未成年者保護制度や親権は、判断能力が不十分である者を救済・保護し、反面、未成年者の自由な権利行使を制限するものであるのに対し、少年法の保護主義は、判断能力が未熟であるが故に非行を犯した者に対し、本人の更生改善を図るとともに、再非行を防止することを目的として保護処分を科すものであり、その目的も内容も全く異なるものである。民事上の取引行為等の場面においては親権には服さなくなった18歳、19歳の年長少年が、その未熟さ故に犯罪行為に至ったというより重大、深刻な場面において、本人の改善更生のため、ひいては再犯防止のために、後見的介入によりその未熟さの原因を解明し、適切な保護処分を科すことは、何ら過剰な介入ではなく、むしろその必要性は高い。
また、現行法においても、婚姻擬制により成年とみなされる者(民法753条)もなお少年法の適用を受けることとされており、また、審判時に20歳未満であった者はその後20歳に達してもなお一定期間保護処分を継続できるが、このことが国家による過度な介入であるとされたことはない。
また、飲酒や喫煙の禁止も、健康被害防止などの本人の利益を保護する観点からの保護主義による介入であるところ、これらについては民法上の成年である18歳、19歳の年長少年に対する後見的介入を維持することとなったことは前述のとおりである。
(イ) また、少年について保護主義に基づく制約を行う根拠は、民法の未成年の場合と共通しており、両制度とも、本人が未成熟であって判断能力が不十分であることに鑑み、本人のためにその自由を制約するものであるとして、民法上の成年年齢が18歳となった場合、親権に服さず、保護の対象にならない18歳、19歳の年長少年について、少年法上類型的に保護の対象とすることは、法理論上整合しないとの指摘もある。
しかし、民事法上求められる取引行為を中心とした一般的な判断能力と、刑事法上の、規範を遵守して、自らの衝動や行動を適切に抑制することまで求められる判断能力とでは、全く異質なものである。
また、民法上の未成年者制度や親権は、全ての未成年者が年齢により一律にその制度に服するものであるのに対し、少年法の保護処分が現実に適用されるのは、資質上あるいは生育環境上のハンディなどから成長発達上の問題を抱えているがために非行に至った者がほとんどであり、少年の中でも特に国家の後見的介入による保護を必要としている者である。
したがって、両制度は、趣旨・目的も内容も全く異なるものであり、その適用対象となる年齢を一致させる必要はない。
(3) 適用年齢引下げにより生じる問題
詳細は後記3において述べるが、少年法適用年齢の引下げは、その理由、必要性がないばかりか、逆に様々な問題をもたらすものである。
少年法適用年齢を引き下げた場合、罪を犯した18歳、19歳の多くは、単に起訴猶予処分となるか、執行猶予付き判決、罰金刑となることが予想され、従来の全件送致主義および家庭裁判所の調査に基づく適切な教育的・福祉的処遇や働きかけを受けられないことになる。罪を犯した18歳、19歳の者の改善更生や社会復帰のための措置が大きく後退することになり、ひいては再犯防止の観点からもマイナスとなる。
更に、少年法の適用対象者が激減すれば、少年のための少年院の施設数も激減し、広域収容に結び付くことが予想される。遠隔地の施設に収容されることにより、家族関係の修復等の環境調整にも困難が生じることになり、少年法適用対象である18歳未満の少年の改善更生や社会復帰にも悪影響が及ぶことが危惧される。
(4) 小括
このように、現行少年法は少年の更生や再犯の防止のために相当程度有効に機能しており、他方、少年法の適用年齢を引き下げるべき立法事実は存在せず、法理論上も引き下げるべき必然性は存在しない上、逆に引き下げにより様々な問題が生じるものである。
3 刑事政策的措置によって少年法適用年齢引下げによる問題を回避できるものではないこと
(1) 総論
ア 部会における議論について
前述のとおり、部会においても、現行少年法が少年の健全な育成を図る上で有効に機能していることについては、争いがない。
すなわち、部会第4回会議において、委員の一名より「今回の議論というのは、現行少年法の下で18歳、19歳の年長少年に対して行われている手続や保護処分が有効に機能していないので、少年法の適用年齢を下げることを検討しようとするものではないのだということについては、意見の一致があると思います。」、「現行法の下での年長少年に対する手続や処遇の有効性という観点からは、少年法の適用年齢を引き下げる必要性はないということになりますので、それ以外の理由があるのかということを検討する必要があるということになろうかと思います。」との発言があったところ、これに対する他の委員からの異論は一切出ていない。部会第5回会議の配布資料(論点表)においても、少年法適用年齢引下げの是非を検討するにあたっては、「少年保護事件の手続過程並びに少年院及び保護観察における処遇が年長少年に対しても有効に機能している中で、『少年』の年齢を18歳未満とする必要性はあるか。」との観点に拠るべき旨の指針が示されている。
結局、部会では、現行少年法が有効に機能していることを委員の誰もが認めているにも拘わらず、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げる旨の結論を先取りした上で、その結果生じる種々の問題点への対策を講じようとしているのであり、不必要な議論に終始するものというほかない。
イ 現在議論されている刑事政策的措置により問題を回避することはできないこと
現在議論されている刑事政策的措置として、少年鑑別所・保護観察所の調査調整機能の活用や、「若年者に対する新たな処分」という制度の創設、刑務所での処遇の充実、保護観察付き執行猶予の活用等があげられている。
しかしながら、これら刑事政策的措置は、あくまでも刑事訴訟法に基づく刑事裁判手続を前提とするものであり、以下に述べるとおり、現行少年法の保護処分が果たしている機能に代替するものとはなり得ない。
(2) 現在議論されている刑事政策的措置により問題を回避することはできないこと(各論)
ア 家庭裁判所調査官による調査調整機能が失われる
(ア) 問題状況
現行少年法は、18歳、19歳の年長少年について、未だ心身の発達が十分でなく、環境その他、外部的条件の影響を受けやすく、その犯罪も深い悪性に根ざしたものではないことから、これに対して刑罰を科するよりは、むしろ教育的な処遇をはかることが適切かつ効果的であるという立場をとっている。
このような趣旨に基づき、現行少年審判手続では、全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査(社会調査)が実施される。家庭裁判所調査官は、心理学や教育学、社会学等の人間関係諸科学を修得した専門職であるが、その知識や技法を活用し、少年や保護者との面談、学校・職場さらには被害者への照会等によって、少年の成育歴や心身の状況、家族・交友関係や生活状況、更には被害の状況等、少年審判及び処遇に必要な事実を把握した上で、そこから得られた情報を評価・分析し、非行メカニズムの解明と再非行可能性の予測を行って、裁判官に対して処遇に関する意見を報告している。
そして、これら詳細な調査結果と意見が記載された「少年調査票」は、裁判官の処遇決定における重要な資料とされるだけでなく、その後少年院や保護観察所へと引き継がれ、処遇にあたっても有用な資料とされている。さらに、家庭裁判所調査官は、その調査手続の過程を通じ、対象となる少年や保護者に対し、いわゆる「教育的措置」も含め、様々な教育的な働き掛けを行っている。
このように、現行少年法制では、対象者の適切な処遇をはかる上で、家庭裁判所調査官の調査が中核的な役割を果たしているのである。
これに対し、刑事訴訟法に基づく刑事裁判手続では、裁判所にも検察庁にも、家庭裁判所調査官に相当する調査機構は存在しない。また、刑事裁判においては、犯罪の背景にある対象者の問題性それ自体が立証の対象とならないため、対象者の問題性を解明するための手続もなく、問題性に対応するための有効な処遇も、十分には選択し得ないことになる。
さらには、手続の過程において、家庭裁判所調査官が行っているような、対象者等に対する教育的な働き掛けも行うことができない。
(イ) 少年鑑別所・保護観察所の調査調整機能の活用
これに対し、家庭裁判所調査官に相当する調査に代替するものとして、少年鑑別所・保護観察所の調査調整機能の活用が検討されている。
しかしながら、少年鑑別所・保護観察所は、家庭裁判所調査官とは専門性が異なり、社会調査に関する経験の蓄積が必ずしも豊富ではなく、家庭裁判所調査官と同様の調査及び働き掛けを期待することはできない。具体的には、少年鑑別所は、主に一定の期間鑑別所において観護措置を取られている少年自身を対象とし、少年の性格や能力といった資質を鑑別する機関である。被疑者の成育歴や家庭環境についての調査能力は限定されているし、被疑者の今後の更生のための有機的な処遇を助言することはできない。また、保護観察所は、もともと裁判所による処分が決定された後にその処分に基づく被疑者の処遇に携わる機関に過ぎず、少年の要保護性の調査のようなことは行えない。そもそも、少年法の「健全育成」という目的に基づかない少年鑑別所・保護観察所の調査・調整は、現行の家庭裁判所調査官の調査調整機能とは異質なものとならざるを得ない。
その上、捜査手続において少年鑑別所・保護観察所が関与する場合には、捜査機関による取調べとの区別が困難であること、捜査の長期化など様々な問題が生じることが懸念される。また、刑事裁判手続におけるこれら機関の関与は想定されていない。
したがって、いかに少年鑑別所・保護観察所の活用を図ろうとも、現行の家庭裁判所調査官の調査調整機能に代わり得るものではない。
(ウ) 「若年者に対する新たな処分」という制度の創設
また、仮に少年法の適用年齢を18歳未満とした場合に、起訴猶予となった18歳、19歳の年長少年に対する働き掛けとして、「若年者に対する新たな処分」という制度の創設が議論されている。
すなわち、分科会における検討結果として報告された内容では、①罪を犯した18歳、19歳の年長少年について、検察官が訴追を必要としないため公訴を提起しないこととしたものについて、②家庭裁判所が家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行うほか、必要があると認めるときは少年鑑別所での鑑別を求めることができることとし、③現行の少年審判に類似した非公開の審判により処分を決定する、といった制度が構想されている。
この制度は、家庭裁判所調査官を活用して司法機関が処分を決する仕組みではあるものの、18歳、19歳という、あくまでも保護主義に基づく少年法の対象外の者に対する刑事訴訟法上の手続を前提とした刑事政策的措置であるから、行為責任主義が妥当する。
そして、起訴猶予が相当とされるような比較的軽微な事案が対象となる以上、収容鑑別は例外的とされ、また、裁判所が下しうる処分についても施設収容処分は認めがたく、在宅での保護観察のみ認められるにとどまるものとなる。また、いかに家庭裁判所調査官を活用するといっても、保護観察処分を上限とする中で、本来の要保護性の判断など不可能と言わざるを得ない。
さらにいえば、そもそも、18歳、19歳の年長少年に対して、何故起訴猶予の判断を行うところまでは行為主義が妥当し、その後家庭裁判所が関与することになると要保護性を基準として処分決定できるようになるのかということが原理的に説明できない。
したがって、「若年者に対する新たな処分」という制度を創設し、家庭裁判所調査官を活用するといっても、行為責任主義の範囲内における処分を前提とした要保護性の調査、判断に実効性などなく、現行少年法の制度に代わるものとはなり得ない。
イ 刑務所収用による問題
(ア) 少年院ではなく刑務所収容になってしまう
少年法の適用年齢を引き下げた場合、現在は少年法に基づき「健全育成」目的で「性格の矯正」を図る少年院教育を受けている18歳、19歳の年長少年のほとんどは、起訴猶予若しくは執行猶予又は罰金刑となることとなり、さらに、重大な犯罪や、犯歴が多い者については、刑務所で収容刑務作業中心の処遇を受けることとなる。
このうち、刑務所収容の場合、少年法に基づき「健全育成」目的で「性格の矯正」を図る少年院教育を受けることができないこととなる(起訴猶予や執行猶予、罰金刑等についての問題性は後述する)。
(イ) 刑務所における処遇内容の充実により問題を回避することはできない
この点に関して、部会では、自由刑の在り方の見直しや、若年受刑者を対象とする処遇内容の充実等が検討されている。
しかし、刑務所における処遇をいかに充実させたとしても、少年法に基づき「健全育成」目的で「性格の矯正」をはかる保護処分ではない以上、自律性が認められるべき「成人」の人格に対して全面的に介入することは許されず、1日24時間、あらゆる生活場面が指導の対象となっている少年院に比べて、刑務所では、基本的な生活態度などについては大部分が指導の対象とならなくなる可能性が高い。また、18歳、19歳の年長少年が抱える問題性は、個々人によって異なる場合がほとんどであって、定型的な処遇プログラムでは対応できないという特質性があり、少年院では、調査官調査を前提とした上で、担任以外の法務教官も全員が少年の顔と背景を把握するなど、職員と在院者の信頼関係を基盤として個々の場面で指導をするが、刑務所では、調査官調査は前提となっておらず、用意された定型的プログラムによる処遇にとどまる。
さらに、刑務所では、基本的には刑務作業が中心となり、専門的処遇プログラムがどの程度導入できるかといった点も十分に検証されておらず、個別具体的かつ専門的な処遇プログラムが実施されるかどうかは不明である。
少年院では、集団寮で集団を形成して生活する中で、他の在院者の言動に触れ、自身の課題に気づき、学ぶという体験をする。集団の相互作用が、人格的に成長するきっかけや指導の端緒となるが、寮集団を形成しない刑務所での処遇ではこのような「気づき」の機会を得ることはできないし、そもそも、18歳、19歳の年長少年が少年法の対象外となれば、少年法の「健全育成」という目的の下で18歳、19歳の年長少年の改善更生を目指してきた処遇のレベルの低下をもたらす危険性がある。
(ウ) 少年院の広域収容による問題等
また別の観点の問題として、18歳、19歳の年長少年が少年法の対象から外れれば少年院の施設数は激減し、それにより必然的に少年院の広域収容に結びつくこととなる。少年の改善更生のためには親子関係の修復も極めて重要な要素であるところ、遠隔地の施設に収容された場合、家族の面会や施設行事のための来院が困難になる可能性が高まり、それによって保護調整も困難になることが危惧される。
実際に、広域収容のケースで保護者との環境調整に苦労する傾向は、東北少年院・青葉女子学園では以前から現実の問題となっているところ、少年院の統廃合の傾向が加われば、問題が深刻化することは明らかである。
以上のとおり、いかにその内容を充実させようとも、刑務所における処遇は、少年院における教育とは大きく異ならざるを得ず、18歳、19歳の年長少年に対する処遇効果においても遠く及ばないものと考えられるし、広域収容による環境調整の難航といった問題も生じうるのであるから、刑務所における処遇改善により、上記問題を克服することは不可能である。
ウ 執行猶予になった場合に更生への支援ができない
少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられた場合、現行法下で少年院送致の処分を受けている18歳、19歳の年長少年うち、一定の割合の者は、成人として初犯であること等を理由に、自由刑に執行猶予が付されることが想定される。
また、現行少年法の下では、保護処分としての保護観察を受けている18歳、19歳の年長少年の一部も、自由刑の執行猶予付き判決を受けるということが想定される。
しかし、例えば2017年に全国の地方裁判所及び簡易裁判所において全部執行猶予付きの懲役刑を宣告された被告人のうち、裁量的保護観察が付された割合は、被告人が21歳以下の者に限定すると、12%前後であって(第1分科会第7回会議議事録4頁・福島幹事発言)、このような現状からすれば、執行猶予付き判決を受けた18歳、19歳の年長少年については、ほとんど何らの働きかけも行われずに放置される危険性がある。
これに対して、部会では、刑の全部の執行猶予制度の在り方を見直し、保護観察付き執行猶予の期間内の再犯についても再度の執行猶予を言い渡すことができるようにして、保護観察付き執行猶予の活用を図ろうとする意見が出されている。
しかし、実際に自由刑の執行猶予に保護観察を付するかどうかは、個々の裁判官の判断に委ねざるを得ない事項であり、また、家庭裁判所調査官による調査が前提とされていないため、わずかな資料しか保護観察官の手元には届かず、対象者の問題性等を十分に把握したうえでの処遇や、更生意欲の高い処遇決定後の早い段階から的確な個別処遇を行うといったことが困難となる。
以上からすれば、現在検討されているような形で、刑の全部の執行猶予制度の在り方を見直したとしても、執行猶予となる18歳、19歳の年長少年に対しては、有効な対応策になっているとは言いがたい。
エ 罰金刑となった場合に更生への支援ができない
現行少年法下であれば、比較的軽微な罪を犯した18歳、19歳の年長少年など、成人であれば罰金刑となるような事件に関しても、家庭裁判所調査官による調査や調整活動等が行われ、審判で保護観察処分となれば、保護観察官及び保護司からの指導監督を相当期間受けることになる。
しかし、18歳、19歳の年長少年が少年法の対象外とされた場合、上記のような者の多くが略式手続を中心とした罰金刑の対象とされ、何らの手当てもされなくなることとなる。
そもそも罰金刑の長所は、自由刑のように社会関係を断ち切ることなくドライに処理できる点にあるものであって、社会生活が安定せず、また安定した収入を得る状態にないことが多いと思われる年齢層の者にとっては痛みが大きくなりすぎるおそれがある。
一方で、若年者の場合は、実際に罰金を負担することになる者は対象者本人ではなく親族等になるケースも少なくないと考えられること等から、刑罰の感銘力さえ乏しいという問題もある。
これに対し、部会では、罰金の保護観察付き執行猶予の活用が検討されている。これは、検察官が有用・相当と判断した場合には、公判請求すべきか否かを検討した上、裁判所に保護観察付き執行猶予の判断に資する事実を主張・立証する、というものである。
しかし、罰金刑の大半は、略式命令請求による裁判(略式手続)で科されているところ、略式手続において、保護観察付き執行猶予とするか否かの判断は、被告人が在廷せず、書面審査のみによっている以上、仮に検察官が資料を提出するとしても、現実的には困難と言わざるを得ない。さらに、上記の過程において調査官が関与するような仕組みが構築されたとしても、保護観察処分に限定された、それも罰金と引き換えの調査ということになれば、本来の健全育成とは全く無縁の調査に終わると考えられ、実効性のある調査がなされるとは言い難い。
また、罰金刑の保護観察付き執行猶予は、自由刑の場合とは異なり、保護観察の遵守事項に違反しても罰金を納付すれば刑の執行が終了するため、威嚇力に乏しく、刑事政策として甚だ疑問のある制度といわざるを得ない。
以上からすれば、罰金の保護観察付き執行猶予の活用によって、罰金刑を言い渡されるであろう18歳、19歳の年長少年に何らかの教育的な処遇を実施しようとしても、それには自ずから限界がある上、実効性にも乏しい。
オ 起訴猶予処分となった場合に更生のための処遇ができない
(ア) 現行法下での取扱
a 現行少年法の下で、全件送致主義が取られており、調査官調査を中心として家庭裁判所による教育的な働きかけがなされていることは、前出のア(ア)で詳述したとおりである。
すなわち、現行法下では、18歳、19歳の罪を犯した年長少年たちは、全員が、犯罪内容の軽重にかかわらず、更正して社会に適応して生活してゆくための1人1人に適した福祉的・教育的処遇を受けられる機会を与えられているのである。
b 他方、成人の刑事事件の取扱はというと、近年の起訴率はおよそ3割超であるから、罪を犯した者のうち7割近くは起訴猶予となってその時点で刑事手続が終了することとなる。
従って、仮に現行少年法の対象を18歳未満に引き下げると、18歳、19歳で罪を犯した年長少年のうち比較的多数の者が、単に起訴猶予処分となって、何らの福祉的・教育的処遇も受けられないまま放置されてしまうこととなってしまうのである。
(イ) 対応策として考えられている起訴猶予に伴う再犯防止措置の問題点
a 上記のような事態に対応するため、部会では各分科会において様々な刑事政策的措置案を検討したが、その内の1つとして「検察官による起訴猶予に伴う再犯防止措置」がある。
これは、「検察官が、被疑者が罪を犯したと認める場合において、必要があると認めるときは、被疑者が守るべき事項を設定し、所定の期間、被疑者を保護観察官による指導・監督に付する措置をとることができるものとする」というものである。
しかしこの「検察官による起訴猶予に伴う再犯防止措置」には、以下の通り極めて問題点が多く、かつその効果にも疑問がある。
b まず、そもそも、判決を経て有罪となっていない被疑者について、検察官が不利益処分である保護観察官の指導等の措置をとることは、無罪推定の大原則に抵触するものである。実際の運用においては、この「再犯防止措置」が実質上の起訴猶予の「条件」となってしまう恐れが極めて大きい。仮に被疑者の同意を要件としたとしても、起訴の威嚇による心理強制下では、被疑者の任意性に常に疑問がつきまとうし、殊更に未成熟で社会経験や知識も乏しく、しばしば捜査官の取調に対して迎合的になりがちな18歳、19歳の年長少年にとっては、検察官との関係において同意の任意性を担保するのは困難である。
また、再犯防止措置の決定をするに当たっては、ある程度被疑者の性質や生活環境の調査をすることが必要となるが、有罪の認定のないまま再犯防止の目的の下に人格や生活環境の調査を行うことは、被疑者にとっては著しいプライバシーの侵害となる恐れがある。
更には、起訴前に犯罪事実の捜査のみならず、そうした生活環境等の調査まで行うこととなると、捜査・取調べの肥大化を招き、刑事手続の公判中心主義にも反することとなる。
c そのような構造的問題点に止まらず、この再犯防止措置手続に関しては検察官の適格性欠如という如何ともし難い問題点もある。検察官は捜査機関・訴追機関であって、福祉や教育についての専門的知見はなく、18歳、19歳の年長少年に対して要保護性を的確に判断して効果的かつ適切な指導・監督内容を定めることは困難である。
このような問題点を補うために、部会では再犯防止措置における処遇方針策定にあたり少年鑑別所や保護観察所の調査機能を活用するという案が出された。しかしながら、少年鑑別所や保護観察所の調査機能に限界があることは、前記3の(2)の(イ)において指摘したとおりであり、両者による調査では到底現行少年法下での調査の代替など担いようがなく、それによっても18歳、19歳の年長少年が少年法の下での処遇を受けられなくなることの不利益は回復できない。
また、こうしたそもそもの少年鑑別所や保護観察所の調査能力の限界に加えて、仮に再犯防止措置手続において少年鑑別所や保護観察所が調査を行うことになる場合、どの段階で、何をどのようにどの程度調査するのか、それを誰が決定するのかなどの具体的な方法は部会の議論によっても全く明らかになってはいない。
d 結局、「検察官による起訴猶予に伴う再犯防止措置」については、構造的に無罪推定原則に抵触し捜査・取調の肥大化を招く等の根本的かつ構造的な問題がある一方で、罪を犯した18歳、19歳の年長少年の内多数の者が更正のために効果的な福祉的教育的処遇を受ける機会を失ってしまうという問題を解決することはできないのである。
(ウ) 対応策として考えられている「若年者に対する新たな処分」の問題点
a 多くの18歳、19歳の年長少年が不起訴になった場合に生じる問題点への対応としては、前述の「若年者に対する新たな処分」の導入も対策として検討されている。
しかしながら、前述のとおり、この制度はそもそも、18歳、19歳の年長少年に対して、何故起訴猶予の判断を行うところまでは行為主義が妥当し、その後家庭裁判所が関与することになると要保護性を基準として処分決定できるようになるのかということが原理的に説明できない。
b また、前述したとおり、この制度では、結果として事実上施設収容処分は認めがたく、在宅の保護観察が処分の上限ということになり、その状況下での本来の要保護性の判断は望めない。仮に収容処分可能としたとしても、かなりの短期間とせざるを得なくなり、そうであれば本来の矯正効果は期待できないばかりか、社会関係の断絶という自由拘束のマイナス効果の方が表に出ることになる危険性が高い。
c 更に、この処分と前述の「起訴猶予に伴う再犯防止措置」との関係も不明瞭である。仮に、検察官による起訴猶予に伴う再犯防止措置が取られた後に、この処分が取られることになると、当事者である18歳、19歳の年長少年にとっての不利益・負担が大きくなりすぎることが懸念される。また、前者で行われる鑑別所なり保護観察所なりによる調査と、後者で行われる調査官調査との関係も不明であり、結局、18歳、19歳の年長少年にとって有機的かつ効果的な働きかけは期待できないと言わざるを得ない。
(エ) 小括
以上のとおり、検察官による起訴猶予に伴う再犯防止措置を導入しても、若年者に対する新たな処分を創設しても、18歳、19歳の年長少年の多くの者が不起訴になってしまうことにより、それらの者に更生のための働きかけを行う機会がなくなるという現実的な不利益を補うことは到底できないのである。
現行少年法での処遇の効果が認められており、18歳、19歳の年長少年にとっては、現況で再犯防止を含む更生のために有効な処遇が受けられることになっているのに、何らの代替手当もできないまま敢えてその機会を奪う必要などどこにもない。
(3) その他の課題
以上の問題点のほかにも、少年法の適用年齢の引下げによって様々な問題が生じることが懸念される。
たとえば、少年法61条は、未だ成熟した判断能力を有しない少年の事件について、少年及びその家族の名誉・プライバシーを保護することにより少年の立ち直りや更生を図ろうという観点から、少年事件の実名報道等を禁止しているところ、少年法の適用年齢が引き下げられれば、仮に18歳の者が罪を犯した場合に、事件の内容や背景事情等にかかわらず、また起訴猶予となるような事案であっても、対象者の特定が可能な報道がなされる可能性がある。しかし、一般に18歳は高等学校に在籍している年齢で、進学や就職を控えた大切な時期でもあり、そのような時期に事件の背景事情等の考慮もなされないままに推知報道がなされてしまえば、当該対象者の社会復帰や改善更生にとって大きな問題が生じかねない。さらに、高等学校においては、同じ学年に少年法が適用される生徒と適用されない生徒が混在することになるため、共犯事件の場合等、行為責任や要保護性の程度にほとんど差異がない事案であるにもかかわらず、一方の生徒のみ推知報道がなされるといった不合理な区別も生じかねない。そして、少年法の適用対象となる生徒とそうでない生徒が混在する状況は、非行やいじめ問題に関する学校教育の場面においても、その教育や指導の仕方について現場に混乱を生じさせることが予想される。しかしながら、これらの点についても十分な検討がなされているとはいえない状況である。
(4) 小括
以上述べたとおり、現在、法制審議会において検討されている若年者に対する刑事政策的措置その他代替案によっては、上記のような問題を回避・解消することはできない。
4 結語
現行の少年法における全件送致主義と保護主義に基づく、調査官調査を中心とした少年への教育的な働きかけは、非行を犯した少年の更生及び再犯防止に相当の効果を上げてきた。また、少年法の適用年齢を引き下げるべきであるとする立法事実は存在せず、民法や他の法律との関係においても引き下げなければならない法理論上の必然性は存在しない。他方、少年法の適用年齢を引き下げてしまうと、本意見書において指摘してきたとおり、様々な問題が生じる。
法制審議会の部会において、現行少年法の機能と、適用年齢を引き下げた場合に問題が生じることについて殆ど異論が無いまま、「仮に引き下げた場合に生じる問題に、どのような対応策があるか」という議論をかさねていること自体がそもそも無益と言わざるを得ない。
そして、現在議論されている刑事政策的措置をもってしても、適用年齢を引き下げることにより生じる問題は回避できないということは既に述べたとおりである。
すなわち、いかなる観点からも、少年法の適用年齢を引き下げることに合理性は見いだせない
したがって、当会は、少年法の適用年齢を引き下げることに断固反対する。
以 上