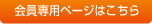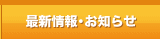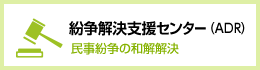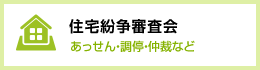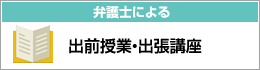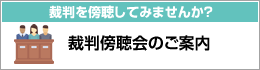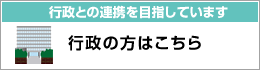日本国憲法が立脚する法の支配・立憲主義が堅持されるよう全力を挙げて取り組む宣言
日本国憲法は、個人の尊重を核心的価値に据え(憲法13条)、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理とする我が国の最高法規であり(憲法98条)、天皇、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う(憲法99条)。すなわち、日本国憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、基本的人権を保障するという法の支配・立憲主義に立脚するものである。
ところが、いま、政府が、日本国憲法や法律の趣旨や文言等を踏まえて確立してきた法解釈や法運用を恣意的に変更するという事態が相次ぎ、憲法が立脚する法の支配・立憲主義が重大な危機にさらされている。
2014年7月1日、安倍晋三内閣は、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。憲法9条の下で集団的自衛権の行使は許されないという政府解釈は、長年にわたる議論によって確立され、堅持されてきたものである。しかるに、憲法の基本原理の一つである恒久平和主義(憲法前文、同9条)に係わる憲法解釈を根本的に変更し、集団的自衛権の行使を容認しようとする上記閣議決定は、政府を憲法の制約の下に置くという法の支配・立憲主義に反する。
この違反状態は現在まで継続しているが、とりわけ、2020年は、法の支配・立憲主義に反する政府の行動が顕著であった。
2020年1月31日、安倍晋三内閣は、国家公務員法を適用して、東京高検黒川弘務検事長の勤務延長の閣議決定を行った。準司法官として政治的中立性と独立性が求められる検察官について、検察庁法32条の2及び22条が国家公務員法の特別法として検察官の定年を定めている以上、国家公務員の定年延長を定めた国家公務員法81条の3第1項が検察官に適用される余地はない。従前の政府解釈も同様であったが、上記閣議決定は、国会等での議論も経ずに従前の確立した解釈を覆したものであり、違法であるばかりか、憲法が要請する司法権の独立(憲法76条3項等)を脅かすものである。当会は2020年3月12日付「東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明」で強く抗議したが、現在まで政府は上記閣議決定の誤りを認めていない。
また、菅義偉内閣総理大臣は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した候補者のうち6名の任命を拒否した。「(同会議の)推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」という日本学術会議法7条2項の規定は、学術研究機関の自律性を保障する憲法23条の趣旨を受けたものであり、内閣総理大臣の任命行為は形式的なものにすぎないとの解釈が確立している。上記の任命拒否は、かかる確立した解釈に反して違法であるばかりか、憲法23条にも違反する。当会は2020年10月22日付「日本学術会議会員の任命拒否を撤回し、同会議が推薦した6名の候補者を同会議会員に任命することを求める会長声明」で強く抗議したが、未だ任命されていない状態が続いている。
政府が、日本国憲法や法律の趣旨や文言に基づき確立してきた法解釈や法運用を国会の審議すらも経ずに変更する事態が相次ぎ、そのような事態が常態化しつつあることは、法の支配・立憲主義に立脚する日本国憲法の危機にほかならず、断じて容認することはできない。新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、国家権力と人権との緊張関係が高まりつつあるいまこそ、法の支配・立憲主義が堅持されなければならない。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士(弁護士法1条)の団体として、政府が日本国憲法や法律の趣旨や文言等を軽視して恣意的な法解釈・法運用を行うことに強く反対するとともに、日本国憲法が立脚する法の支配・立憲主義が堅持されるよう、全力で取り組むことを宣言する。
2021年(令和3年)2月27日
仙 台 弁 護 士 会
会長 十 河 弘
提 案 理 由
1 日本国憲法の立憲主義と「法の支配」原理
立憲主義とは、国家権力を行使する者に対し、憲法によってその権力に縛りをかけ、濫用を防止するものであり、「法の支配」原理と密接に関連する。「法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものであり、日本国憲法も、個人の尊重を核心的価値に据え(憲法13条)、基本的人権の永久・不可侵性を確認するとともに(憲法11条、97条)、憲法の最高法規性を確認し(憲法98条)、公務員に憲法尊重擁護義務を課していること(憲法99条)、また、法の内容の正しさと適正な手続の保障を定め(憲法31条)、それを実質的に機能させるために司法権の独立を保障し(憲法76条以下)、裁判所に違憲立法審査権を付与していること(憲法81条)から、日本国憲法が「法の支配」に立脚していることは明らかである。
しかしながら、いま、政府が、日本国憲法や法律の趣旨や文言等を踏まえて確立してきた法解釈や法運用を恣意的に変更するという事態が相次ぎ、日本国憲法が立脚する法の支配・立憲主義が重大な危機にさらされている。
2 集団的自衛権行使容認の閣議決定と安全保障関連法の制定
(1)憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認
2014年7月1日、安倍晋三内閣は、内閣総理大臣の私的な諮問機関の答申を踏まえ、これまで長年堅持してきた政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認する旨の閣議決定をした。
この点、集団的自衛権とは、政府解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」とされる。しかしながら、前文で平和的生存権を確認し、9条で戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を定めるなど、徹底した恒久平和主義を採用している日本国憲法のもとでは、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、外国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利である集団的自衛権を行使することは許されない。
日本国憲法は国家の統治原理を示すものであるから、政府は憲法前文及び9条に示された統治原理(徹底した恒久平和主義)に反する政策や憲法解釈を採ることは、法の支配・立憲主義の見地から許されない。そして政府も、自衛権の行使は、それが許容される3要件(①わが国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)が存在すること、②この攻撃を排除するため、他の適当な手段がないこと、③自衛権行使の方法が必要最小限度の実力行使にとどまること)に該当する場合でなければならず、集団的自衛権の行使は①の要件を満たさないため、憲法上許されないという立場を60年以上にわたって堅持していたのである。
以上のとおり、集団的自衛権の行使は日本国憲法上許容されないという政府解釈は長年にわたる議論によって確立され堅持されてきたものであった。ときの政府や国会の判断で解釈を変更してこれを根本的に変更することは、憲法を最高法規と定め(10章)、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(98条)、国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課すことにより(99条)、政府や立法府を憲法の制約のもとに置こうとした法の支配・立憲主義に違反し、到底許されるものではない。
(2)安全保障関連法の制定
2015年9月19日未明、いわゆる安全保障関連法案が参議院本会議で強行採決され可決成立した。本法は、わが国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、他国間の戦争に加わっていくことを意味する集団的自衛権の行使を可能とするとともに、他国軍隊に対する兵站支援や武器防護のための武器使用などを認めるものである。本法は、集団的自衛権の行使を容認するという根幹部分において、戦争、武力による威嚇及び武力の行使を放棄した憲法9条に違反するうえ、「存立危機事態」の概念の不明確性から、ときの政府・与党の判断により歯止めのない集団的自衛権行使が行われる危険性も高い。また、本法が予定する他国軍隊への支援活動は、他国の武力行使との一体化が避けられないなど、本法は多くの基本的な部分で憲法に違反している。このような憲法違反の法制度を作ることは立憲主義の否定であり、法の内容の適正を要求する法の支配に反するものに他ならない。
(3)違憲状態の継続
上記集団的自衛権行使容認の閣議決定や安全保障関連法の制定に対し、当会は違憲であることを指摘し続けてきた(2013年10月18日付「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対する会長声明」、2014年5月3日付「憲法記念日に当たって集団的自衛権の行使容認に改めて反対する会長声明」、2014年7月1日付「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議しその即時撤回を求める会長声明」、2015年2月21日付「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定の撤回を求めるともに同閣議決定に基づく法整備に強く反対する決議」、2015年6月17日付「憲法違反の安保関連法案に反対し、その廃案を求める会長声明」、2015年7月17日付「安保関連法案の衆議院採決の強行に抗議し、本法案の廃案を求める会長声明」、2015年9月19日付「安全保障関連法案の参議院採決の強行に強く抗議し、同法の廃止を求める会長声明」、2016年2月27日付「安全保障関連法等の廃止を求め、立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を訴える決議」、2016年10月20日付「憲法違反の安保法制の廃止を求めるとともに南スーダンPKOに対する運用・適用に反対する会長声明」)。しかし、現在においても安全保障関連法は廃止されておらず、違憲状態は、いまもなお継続している。
3 東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定について
(1)検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。東京高等検察庁の黒川弘務検事長は「その他の検察官」にあたり、2020年2月7日に退官する予定であった。ところが、安倍内閣は、同年1月31日の閣議で、国家公務員法81条の3第1項の規定を根拠に黒川検事長の定年延長を決定した。
(2)国家公務員法81条の3第1項は、任命権者は、定年に達した職員が退職すべきこととなる場合において、「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは」、定年退職予定日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、その職員の定年を延長することができるとしている。
しかしながら、検察官も国家公務員ではあるが、国家公務員の身分や職務に関する一般法である国家公務員法とは別に、検察庁法が特別法として、検察官の定年を定めているのであるから(検察庁法32条の2)、国家公務員法81条の3第1項が検察官に適用される余地はないというべきである。しかも、国家公務員法81条の3が新設された1981年当時の国会審議では、人事院が検察官にはこの規定は適用されないという考え方を示したことを踏まえて同規定を含む法案が可決成立しており、立法者意思は明確に示されていた。条文構造から見ても、国家公務法81条の3第1項は、「前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」とし、同法81条の2(定年による退職)を前提にした勤務延長を規定するが、検察官には同法81条の2の適用はない以上、同条を前提とする国家公務法81条の3の適用も当然にない。
(3)安倍晋三前首相は、2020年2月13日の衆議院本会議で、上記政府見解の存在を認めた上で、安倍内閣として閣議決定で解釈を変更したことを明言した。しかしながら、上記のとおり、国家公務員法81条の3は検察官には適用がないことを前提に国会で審議され制定されたものである。それをときの内閣の都合で国会の審議も経ずに変更することは、国会の立法権を軽視するものであり、三権分立の趣旨に反する。そもそも、検察庁は「検察の理念」として「厳正公平、不偏不党を旨として、公正誠実に職務を行う」ことを掲げている。刑事司法の一翼を担い、強大な捜査・訴追権限を有している検察官の人事のルールは、国政上の最重要事項の一つであり、全国民を代表する国会の審議・決定をも経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない。ときの政権の都合で検察官の人事のルールを変更するなどということは、内閣による検察官への人事的コントロールを拡大しかねず、日本国憲法が要請する司法権の独立を脅かすものであるし、こうした重大事項について、立法者意思を無視し、従来の法解釈を恣意的に変更してかまわないということでは、法の支配の否定にほかならない。
したがって、黒川検事長の定年延長を認めた閣議決定は、検察庁法22条及び同法32条の2に違反するとともに、法の支配に反する。
(4)当会は、2020年3月12日付「東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明」並びに2020年4月24日及び2020年6月25日の各会長声明と、三度にわたって強く抗議したが、現在まで政府は上記閣議決定の誤りを認めていない。
(5)ところで、政府は、2020年3月13日、検察庁法改正案を含む国家公務員法等一部を改正する法律案を通常国会に提出した。この検察庁法改正案は、後に廃案となったものの、その内容は全ての検察官の定年を現行の63歳から65歳に引き上げた上で、63歳の段階でいわゆる役職定年制が適用されるというものである。そして、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生じる」と認めるときは、役職定年を超えて、あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるようなものであった。この改正案によれば、上記閣議決定のような検察官人事への政治の恣意的な介入が可能となり、準司法官として職務と責任の特殊性を有する検察官に強く求められる政治的中立性や独立性が脅かされる危険性があまりにも大きく、憲法の基本原理である権力分立に反する。仮にこの改正案が運用される事態となれば、検察権行使が歪められ、政治家への追及がなおざりになるおそれが生じ、厳正、公平、不偏不党を旨とする検察に対する国民の信頼が根底から失われることにつながる。
したがって、国会による審議を経たとしても、上記改正案のような内容であれば、検察官の政治的中立性や独立性が脅かされ、憲法の基本原理である権力分立に反する。それゆえ、国会による法改正を経たとしても、その内容の憲法適合性は問題となるところ、上記改正案は憲法の基本原理たる権力分立に反し、法の内容の適正を要求する「法の支配」に反することを付言する。
4 日本学術会議会員の任命拒否問題
(1)菅義偉内閣総理大臣(以下、「菅首相」という)は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した候補者105名のうち6名の任命を拒否した。
任命拒否の理由について、菅首相からは、「(日本学術会議の)総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」と説明がされている。
(2)日本学術会議は「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし」て設立された組織であり(日本学術会議法前文)、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的と」し(同法2条)、科学に関する重要事項の審議・実現及び科学に関する研究の連絡・能率向上の職務を「独立して」行うと定められている(同法3条)。上記の「独立して」とは、同会議が政府から干渉やコントロールを受けずに、政府から独立した自律的な組織として職務を行うということである。同法1条2項が日本学術会議と内閣総理大臣の関係を「指揮」や「監督」ではなく、「所轄」にとどめているのも、日本学術会議の自律性を重視しているからにほかならない。
日本学術会議の会員の任命は、同会議が「優れた研究又は業績のある科 学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するもの」とし(同法17条)、「17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法7条2項)とされている。「優れた研究又は業績」という選考基準を満たしているかどうかを適切に判断することができるのは、日本学術会議であり、内閣総理大臣ではない。
また、内閣総理大臣は、日本学術会議の会員自身から病気その他やむを 得ない事由により自発的な辞職の申し出を受けたときでさえも、辞職を承認するには日本学術会議の同意を要するとされており(同法25条)、また、会員として「不適当な行為」がある場合すら、同会議の「申出に基づ」かなければ、退職させることができない(同法26条)とされ、任命権と表裏一体の関係にある辞職の承認権及び解任・解職権についても法律上著しく大きな制限が課されている。
日本学術会議法制定当初は、日本学術会議の会員は、全国の科学者により選挙されていたが、1983年、学会を基礎として選出された者を日本学術会議が会員候補者として内閣総理大臣に推薦し、その推薦に基づき内閣総理大臣が任命する方法とする法改正が行われた。法改正当時の政府は、国会の委員会において、内閣総理大臣による会員の任命行為(同法7条2項)は、同会議の推薦に基づいて行われる形式的なものにすぎないとの解釈の下、内閣総理大臣は推薦された候補者を拒否せず、そのまま任命すると答弁したが(1983年5月12日参議院文教委員会における中曽根康弘内閣総理大臣及び政府委員答弁、同年11月24日参議院文教委員会における丹羽兵助総理府総務長官答弁)、そのような国会答弁は今日まで変更されていない。
以上によれば、内閣総理大臣の任命権は形式的なものであり、内閣総理大臣は日本学術会議の推薦のとおりの会員を任命しなければならないという解釈がすでに確立している。
菅首相は、今回の任命拒否の理由について「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から」であると説明しているが、日本学術会議法上そのような理由による任命拒否は認められていないことは上記の国会答弁からも明らかである。
したがって、菅首相による新会員候補者6名の任命拒否は、日本学術会議法の確立された解釈を誤ったものであり、違法である。
(3)加えて、今回の任命拒否が、拒否された会員候補者の学問研究内容ないし学問的知見の表明を理由とするものであるならば、それは各会員候補者の学問の自由(憲法23条)を侵害するものであることは明らかである。
また、日本学術会議の会員の任命について上記のような解釈を行うのは、憲法23条によって保障される学術研究機関の自律性を確保することにある。すなわち、日本国憲法が思想良心の自由(憲法19条)や表現の自由(憲法21条)とは別に第23条で学問の自由を保障した条項を設けたのは、学問研究の成果が、しばしば社会の既成の価値観や時々の政府の政策を批判するものであり、そのために社会や政治権力の側から敵対的反応を招きがちであることにかんがみ、外部の政治的・経済的・社会的圧力に対する各学問研究の自律性・独立性を保護すべき必要性があるからである。
日本学術会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること」を目的とし、全ての学術分野の科学者を擁し、幅広い科学的知見を結集して、科学の向上発達のため、従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする学術の専門分野の研究組織であり、その目的を達成するためには、憲法23条によって自律性・独立性が保障されなければならない。それゆえ、日本学術会議法も、上記のとおり会員の人事について同会議の独立性・自立性を強く認めているのである。
今回の任命拒否は、内閣総理大臣による日本学術会議への人事的コントロール権限を制限した憲法23条及び同法に基づく日本学術会議法を否定するものであって、法の支配・立憲主義に違反する。
(4)なお、菅内閣は、憲法15条1項を根拠に正当性を主張している。しかし、憲法15条1項は、公務員の選定・罷免の正統性の根拠が主権者である国民にあることを定めたものであり、内閣総理大臣に公務員の包括的な選定・罷免権を授権したものではない。公務員の選定・罷免は、内閣の権能について定めた憲法73条4号に「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」とあるとおり、法律の定める基準によらなければならず、日本学術会議会員について言えば、日本学術会議法7条2項及び17条に従わなければならない。このように、6名の任命拒否は同条項の基準に従っているとは認められず、法的正当性は認められない。法的正当性が無いにもかかわらず、憲法15条を恣意的に解釈して任命拒否権限があるかのように主張することは、法の支配、立憲主義の否定というほかない。
(5)当会は、2020年10月22日付「日本学術会議会員の任命拒否を撤回し、同会議が推薦した6名の候補者を同会議会員に任命することを求める会長声明」で強く抗議したが、未だに上記6名の任命はされておらず、現在まで是正されていない。
5 むすび
これまでに掲げた動きに見られるとおり、政府が、日本国憲法や法律の趣旨や文言等を踏まえて確立してきた法解釈や法運用を国会の審議も経ずに変更するという事態が相次ぎ、そのような事態が常態化しつつあることは、法の支配・立憲主義に立脚する日本国憲法の危機にほかならず、断じて容認することはできない。コロナ禍で、国家権力と人権との緊張関係が高まりつつあるいまこそ、法の支配・立憲主義が堅持されなければならない。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士(弁護士法1条)の団体として、政府が日本国憲法や法の趣旨や文言等を軽視して恣意的な法解釈や法運用を行うことに強く反対するとともに、日本国憲法が立脚する法の支配・立憲主義が堅持されるよう、全力で取り組むことを宣言するものである。
以上